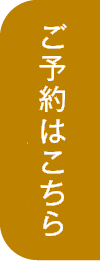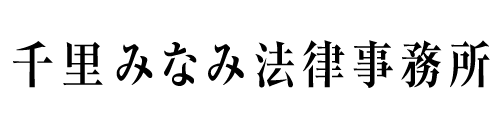【大阪の離婚弁護士が教える】父親が子の監護者に指定された事例②
これは、父親が子どもと一緒に暮らしているというケースにおいて、父親が監護者に指定された事例です。
【東京高裁平成28年5月13日】
2 監護者の指定について
(1) 別居中の夫婦間において、子の監護をめぐる争いがあり、当事者間で協議が整わない場合には、民法766条の類推適用により、家庭裁判所が子の監護者の指定その他子の監護に関する事項を定めるのが相当である。
(2) そこで、前記1で引用する原審判の「理由」中の「第2 当裁判所の判断」の1の認定事実(ただし、補正後のもの。以下、単に「認定事実」という。)に照らし、未成年者らの監護者の指定について検討する。
ア 当事者双方の監護の状況等
(ア) 未成年者らとの愛着関係
相手方は、平成26年4月(長男が2歳、二男が10か月)に未成年者らを保育園に入園させて職場復帰するまでは、平成24年中の数か月の夜間のキャバクラ店でのアルバイト勤務以外には、家事育児に専念して、未成年者らの監護に関する事項全般を中心になって担当していたこと(認定事実(1)ないし(3))、相手方が平成26年4月に職場復帰した以降、抗告人と相手方との間では、未成年者らの監護は主として相手方が行うことが前提となっており、保育園とのやりとりは主に相手方が行っていたが、相手方が飲み会に出るなどと言って遅く帰ったりするようになる一方、抗告人はその勤務体制から自宅にいる日も多く、未成年者らが病気の際の看護、相手方が遅く帰宅するときの未成年者らの食事及び入浴の世話、寝かしつけといった育児家事を抗告人が行うことが増えていったこと(認定事実(4))、家庭裁判所調査官の家庭訪問時の未成年者らの様子によれば、未成年者らは、抗告人及び相手方の双方に親和し、双方に対し、愛着を示していること(認定事実(12))が認められる。
以上によれば、長男については、2歳になるまで基本的に相手方が自宅で監護してきたことから、長男は相手方を愛着対象として成長、発達を遂げてきたといえるが、2歳で保育園に通園するようになると、保育士らの監護を受けるとともに、また、抗告人が監護する機会も増えて、相手方を中心としつつも、抗告人とも愛着関係を形成するようになったものということができる。
他方、二男は、生後約10か月で保育園に通うようになり、早期の段階から多くの大人の監護の下に置かれており、それらの大人と多重的な愛着関係を形成して成育してきたものといえ、抗告人と相手方の双方と愛着関係を形成してきたものということができる。
したがって、未成年者らとの接触時間の長短といった量的側面においては、相手方が優り、そうした観点からは、別居時までの未成年者らの主たる監護者は相手方であるといえるが、相手方が平成26年4月に職場復帰して以降は、抗告人の関わりが増え、別居直前までには、抗告人との愛着関係も形成されてきたということができ、未成年者らとの愛着関係に関しては、抗告人と相手方との間において圧倒的な差異があるということはできない。
(イ) 相手方の監護状況
相手方は、育児休業中に、特に必要もないのに、抗告人の反対を押し切り、自ら好んでキャバクラ店で夜間のアルバイトをし、抗告人との約束に反して、抗告人の不在の折にたまたま遊びに来ていた高校時代の友人に生後まもない長男を預けてキャバクラ店のアルバイトに行ったことがあったり、生後まもない長男を連れてCとカラオケやホテルに行ったことがあり(認定事実(2))、これらの行為は、抗告人を裏切る行為であると同時に、相手方の監護姿勢についての不安要素であり、また、相手方の未熟さも窺わせるものである。
また、相手方は、平成26年4月に職場復帰した後、抗告人との間で相手方が時短勤務をして主として育児を行うことを相互に了解しており(認定事実(4))、この役割分担は、抗告人と相手方の収入の差や稼働の目的(相手方自身、抗告人とのメールのやり取りにおいて、抗告人が家族を養うべく稼働しているのに対し、相手方は息抜きや自分の時間の確保のために稼働していることを認める発言をしている(乙47の35頁)。)に照らして妥当なものであるといえるところ、相手方は、同年7月頃から、飲み会等と称して遅くなることが増え、抗告人に対し、謝罪や反省の弁を述べながらも、同じことを繰り返したことや、未成年者らが病気になった際の看護も、抗告人に委ねがちであったこと(認定事実(4))は、抗告人の相手方に対する信頼を喪失させる行為であると同時に、相手方の監護姿勢についての不安要素であり、相手方の未熟さを窺わせるものである。
もっとも、相手方のそうした行動は、抗告人が在宅していて未成年者らの面倒を見られる状況にあったことに乗じたものであり、未成年者らを危険な状態に放置したということとは異なるから、抗告人が主張するような育児放棄であるということはできないが、抗告人の支えがあってこそ、相手方を主たる監護者として、未成年者らが順調に成長、発達してきたということができる。
以上のとおり、相手方には、その監護姿勢が問われるべき部分があったと言わざるを得ないところ、相手方がその両親と同居し、監護補助や指導を受けることによって補い得るとも考えられる。しかし、この点、抗告人は、相手方はトラブルがあれば両親を頼るものの、両親から離れたいという願望がある旨述べており(乙41の25頁)、相手方も、抗告人とのメールのやりとりにおいて、「親と暮らすつもりは一切ないし、これからのことも親は一人で育てるのは無理だって言い切るけど、私はできると思っているから平気。」と述べていたことがあるほか(乙47の32頁)、相手方の陳述書において、「いつまでも両親の世話になるのもおかしな話であるので、未成年者らが小学生になったら引っ越すことを考えている」旨述べており(甲27)、相手方の両親の監護補助や指導が継続的に行われるかどうかは不確実と言わざるを得ない。
(ウ) 抗告人の監護状況
抗告人は、相手方が平成26年4月に職場復帰して以降、家事育児への関わりが増加していき、未成年者らと抗告人との間にも愛着関係が形成されており、相手方と別居してから以降は、抗告人が主として未成年者らを監護しており、未成年者らは、抗告人の監護下で、順調に成長、発達している。
また、抗告人は、相手方と別居後、未成年者らの心情に配慮して、別居開始月の翌月から概ね月2回の頻度で、未成年者らを相手方と面会交流させており、面会交流の際にトラブルが生じても、その後の面会交流を拒否するようなことはせず、また、宿泊を伴う面会交流も認めており(認定事実(8))、未成年者らの監護に関して、自らの相手方に対する感情を抑制して、未成年者らのために適切な対応を行うことができていることは、評価できる事情である。(なお、面会交流時のトラブルについて、一方的に抗告人に非があると認めることはできない。)
イ 以上によれば、当事者間の別居時の段階において未成年者らの主たる監護者は相手方であるといい得るものの、この間の未成年者らの順調な成長発達については、抗告人の支えがあったこと、相手方が職場復帰して未成年者らが保育園に行くようになってから以降は、抗告人の未成年者らの監護への関わりが増し、未成年者らは抗告人との間でも愛着関係を形成してきており、未成年者らとの愛着関係、親和状況の観点においては、抗告人と相手方との間に径庭はないということができる。監護状況の観点からは、相手方の監護姿勢には問題があり、この点は、相手方が未成年者らを監護のする場合の不安要素であると認めざるを得ない上、相手方の監護上の不安要素を補い得る手段となる相手方の両親による監護補助についても、相手方自身がその受け入れに消極的である言動をしている。他方、抗告人による監護状況、監護姿勢に問題は認められない。未成年者らの生活状況の観点からは、平成27年4月20日以来、未成年者らは抗告人と生活をし、家庭生活及び保育園での生活に問題がなく、安定した状態にあるということができ、そのような状態が継続している。その間、未成年者らと相手方との面会交流は、抗告人の受容的な姿勢もあって、定期的に実施されており、今後も継続されることが十分見込まれる。以上のことを総合すると、監護姿勢等に未熟さや不安要素があり、これを払拭し得るだけの具体的事情が認められない相手方に未成年者らの監護を委ねるよりも、安定していて指摘すべき問題の見当たらない抗告人による監護を継続することが、未成年者らの福祉にとって望ましいものと解される。
したがって、未成年者らの監護者としては、抗告人を指定するのが相当である。
(3) なお、抗告人は、抗告理由において、離婚訴訟が係属中の夫婦において、別居中の監護者の指定の審判を求めることができるのは、子の福祉の観点から早急に子の監護者を指定しなければならない場合に限られると主張する。
しかしながら、同主張は独自の見解というべきものである上、同主張の見解によると、離婚訴訟が係属中である限り、子の監護者は原則として現状維持とするいうこととなってしまうが、その場合には実力行使による子の奪い合いを招来しかねず、この点において相当とは解されない上、離婚訴訟係属中の夫婦間の子の監護についても法的判断に基づく秩序の維持又は形成が必要であることは、離婚訴訟が係属していない夫婦の場合と異なるものではない。
したがって、抗告人の上記主張は採用することができない。
3 未成年者らの引渡請求について
前記2のとおり、未成年者らの監護者としては抗告人を指定するのが相当であるから、相手方の抗告人に対する未成年者らの引渡しの申立ては、理由がないというべきである。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。