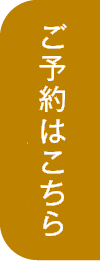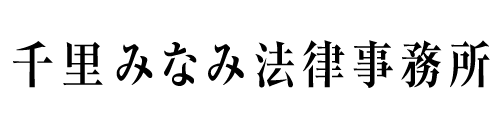【大阪の離婚弁護士が教える】父親への親権者変更を認めた事例③
父親への親権者変更が認められた事例の3つ目を紹介します。
【大阪高裁平成12年4月19日決定】
2 判断
(1) 当裁判所も、事件本人の親権者は抗告人から相手方に変更するのが相当と判断する。その理由は、(2)に付加するほか、原審判理由欄2記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原審判10枚目表1行目の「事件本人のこの意思は」から同6行目の「ならない。」までを、「事件本人のこの意思が、長年同人を監護してきた相手方及びBの意向に影響を受けた可能性は、記録上否定できないと考えられるが、意思の形成過程はともかくとして、事件本人が現在の生活環境から引き離され、抗告人のもとに引き取られるのを強く嫌悪していることは確かであって、事件本人がある程度の自己主張をできる年齢に達していることを考えると、この意思を尊重しなければならない。」と改める。
(2) 当審における抗告人の主張に対する判断
ア 抗告人は、相手方が抗告人によって育てられていた事件本人を抗告人に無断で自己の支配下に置き、抗告人を親権者とする判決が確定しても、引渡要求や強制執行に応じることなく、既成事実を積み上げた上で、正当な権利行使である抗告人の引渡要求が事件本人に不安定さをもたらすことや生活上の不便を理由として親権者変更を申し立てるのは許されず、これを認めた場合には、上記確定判決の拘束力に反する結果となると主張する。
相手方が上記判決に従わず、事件本人の監護を続けていることは原審判認定のとおりであり、この点を抗告人が非難するのはもっともである。しかし、民法819条6項は、裁判で親権者が指定された場合にも適用される規定であり、裁判確定後の事情の変化により親権者を変更することが子の福祉に合致すると認められる場合、家庭裁判所が親権者変更の審判をすることができるのは明らかである。もちろん、非親権者が子を監護するに至った経緯は、上記審判をするに当たり当然考慮すべき事情となるが、本件においては、かかる事情を踏まえた上でなお親権者を相手方に変更するのが相当と解すべきことは、原審判の説示するとおりであるから、抗告人の主張は理由がないといわざるを得ない。
イ 抗告人は、事件本人が現在もなお相手方の違法な拘束下にあり、人身保護法に基づいて事件本人の抗告人への引渡が許容されるべき場合であるから、軽々に親権者の変更をすることは許されないと主張する。
離婚して非親権者となった者による子の監護は、その子が意思能力を有しないか、あるいは有したとしても自由意思に基づいて監護者のもとにとどまっているとはいえない場合には、人身保護法及び同規則にいう拘束に当たり、違法性を帯びると解すべきである。事件本人は既に10歳であるから意思能力は有しているといえるが、前記(1)のとおり、同人が抗告人に引き取られるのを拒んでいる背景には、長年にわたり事件本人を監護してきた相手方及びBからの影響があることが窺われ、事件本人が真に自由意思に基づき相手方及びBのもとにとどまっているのか否かについては、疑わしい面が確かにある。
しかし、自由意思を持たない子に対する離婚後の非親権者による監護が違法とされるのは、同人が親権を有していないからであり、その監護が子の福祉にとって害となるからではない。子の福祉の見地からは、引き続き非親権者に監護を委ねる方が望ましい場合があることも当然考えられるのであって、そのような場合には、むしろ親権者を変更して監護の違法状態を解消させるのが、民法819条6項の趣旨に合致するというべきである。
本件においては、仮に相手方の監護が違法であったとしても、原審判の認定事実によれば、親権者を相手方に変更するのが事件本人の福祉に沿うと認められるから、抗告人の前記主張は理由がない。
ウ 抗告人は、相手方が親権者としての適格性を欠き、また、親権者変更の申立につき保護に値しないと主張し、その理由として、〈1〉婚姻破綻の主たる原因が相手方にあること、〈2〉相手方は暴力的性格を有していること、〈3〉相手方は、事件本人に対し抗告人についての負のイメージを植えつけ、母親である抗告人との暖かな交流を図ろうとしていないこと、〈4〉相手方は、所得控除及びBの生活保護費の受給につき不正な手段を講じていた疑いがあること、〈5〉相手方は、離婚前、長男Cの抗告人及びその父に対する暴言をたしなめようとしなかったこと、〈6〉事件本人はこれまでBと同居してきたのであり、相手方と事件本人との共同生活の実績はないこと、〈7〉相手方は、これまで何度も親権者変更の申立てを行い、取り下げていることなどをあげる。
そこで検討するに、まず、〈1〉、〈4〉、〈5〉については、それが抗告人主張のとおりであるとしても、直ちに相手方の親権者としての適格性を否定する事情となるものではない。〈2〉については、記録によれば、相手方はかつて抗告人に暴力を振るったことは認められるものの、事件本人に対し暴力的な対応をしていることを認めるに足りる証拠はなく、抗告人への暴力の事実が直ちに相手方の親権者としての適格性を否定する事情となるものではないから、抗告人の主張は採用しがたい。これに対し、〈3〉については、前記のとおり、相手方の意向が事件本人の抗告人に対する拒否感情に影響を及ぼしている可能性があるし、〈6〉、〈7〉についても、記録によれば、抗告人主張の事実が認められるところである。これらは、親権者変更の当否を決める際に考慮すべき事情と考えられる。しかし、事件本人が現在の生活環境から引き離され、抗告人のもとに引き取られるのを強く嫌悪している状況下において、事件本人の福祉を唯一・最大限に考慮すると、上記の事情があったとしても、なお、親権者を相手方に変更するのが相当というべきである。したがって、抗告人の主張は理由がない。
これも、父親と子が一緒に暮らしていたという事案です。
ここまで、父親に親権者変更が認められた3つの裁判例を紹介しましたが、いずれも父親と子がすでに一緒に暮らしていた事案でした。
つまり、一般的によく問題になる、母親と子が一緒に暮らしている状況において、父親が親権者変更の申立てを行った事案ではないという点に注意が必要です。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。