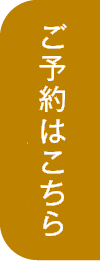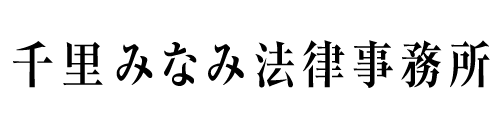【大阪の離婚弁護士が教える】子が祖父母と養子縁組した場合の養育費
前回の記事では、子が再婚相手と養子縁組した場合の養育費に関する裁判例を紹介しました。
では、子が祖父母と養子縁組した場合の養育費はどうなるのでしょうか。
今回は、この点が問題となった裁判例を紹介することとします。
【東京高裁令和5年6月13日決定】
ア 母方祖父母は,本件養子縁組により,同居の孫である未成年者を養子としたところ,一般に,未成年者との養子縁組には,子の養育を全面的に引き受ける意思が含まれると解される上,未成年者養子制度の目的からいっても,未成年者に対する扶養義務は,第一次的には養親が負い,非親権者である実親は,養親が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときに限り,次順位で扶養義務を負うものと解される。
これを本件について見るに,母方祖父母は,25年以上にわたり,不動産の委託管理,駐車場の経営等を目的とする同族会社であるDの代表取締役又は取締役を務め,その本店及び母方祖父母宅の敷地である土地を共有し,Dは,E内に宅地を所有していることは,前記認定のとおりである上,当裁判所が,相手方に対し,母方祖父母の年収が分かる資料及び資産の全体を記載した陳述書等の資料の提出を求めたにもかかわらず,何らの資料が提出されなかったことからすると,養親である母方祖父母は,無資力その他の理由により十分に未成年者の扶養義務を履行することができないと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる資料はない。
以上によれば,本件養子縁組により,未成年者に対する第一次的な扶養義務者は,養親である母方祖父母となり,未成年者の実父である抗告人は,第一次的な扶養義務者ではなくなったことが認められる上,養親である母方祖父母が無資力その他の理由により十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないので,本件においては,前件調停条項3項の基礎とされた事情に変更が生じ,当初の調停合意の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきである。
イ これに対し,相手方は,①養子縁組によって実親の扶養義務が消滅するのは,監護親である実親が再婚し,再婚相手と未成年者が養子縁組をして,実親,養親及び未成年者が家族を形成し,非監護親である実親の権利も義務も排除して子の養育を引き受ける場合を前提としており,祖父母や他の親類が養親となる場合は,実親の存在を排除していないこと,②本件養子縁組後も,相手方は実母として,抗告人からの養育費と自己の収入により未成年者を監護養育してきたことからすると,本件養子縁組をもって,養親である母方祖父母が未成年者の扶養義務を引き受けたと見ることはできず,本件養子縁組の事実は養育費を減額すべき事情の変更には当たらない旨主張する。
しかしながら,上記①の点については,祖父母が未成年者である孫と養子縁組をする場合(民法798条ただし書)でも,未成年者は養父母の共同親権に服することになる以上(同法818条1項ないし3項),養父母は,法的には未成年者の扶養義務を全面的に引き受ける意思を表示したとみるのが自然であり,従前の非監護親である実親に対しては,養父母が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときを除き,同順位での扶養義務の履行を求めるべき理由は見当たらない。
上記②の点についても,本件養子縁組当時,母方祖父は76歳,母方祖母は72歳であり,母方祖父母が,抗告人に対し,未成年者(当時7歳)の養育費の分担を事実上期待する意思を有していたとしても不自然ではないが,前記認定説示のとおり,本件においては,養親である母方祖父母が無資力その他の理由により十分に扶養義務を履行することができないときに当たると認めることができない以上,非監護親である実父に対し,養親である母方祖父母と同順位の扶養義務を課すことはできない。
したがって,相手方の上記主張は採用することができない。
ウ 相手方は,相手方が,抗告人の不貞によって,心身に不調を来たして母方祖父母宅に戻った後,相手方に不慮の事故等があった場合に,母方祖父母に未成年者の面倒を見てもらうために本件養子縁組がされたという経緯からすれば,抗告人が本件養子縁組の事実をもって扶養義務を免れたと主張することは信義則に反するとも主張する。
しかしながら,相手方が本件養子縁組をした趣旨や動機によって,未成年者に対して第一次的に扶養義務を負う者が変わるというのも相当とは解されないから,抗告人が本件養子縁組の事実をもって第一次的な扶養義務者ではなくなった旨主張することが,信義則に反するということはできない。したがって,相手方の上記主張も採用することができない。
(3)小括
以上によれば,その余について判断するまでもなく,本件養子縁組により抗告人が第一次的な扶養義務者ではなくなったという事情の変更により,前件調停条項3項に基づき,抗告人が相手方に対して未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めを取り消すのが相当である。
その取消しの始期については,当事者間の公平や当事者の意向等に鑑み,抗告人が本件審判に移行する前の調停を申し立てた令和3年11月とするのが相当である。
この裁判例は、子が祖父母と養子縁組した場合には、養育費は0円となることを示しました。
ということで、子が再婚相手と養子縁組した場合だけでなく、祖父母と養子縁組した場合にも養育費は0円となる可能性があるといえます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。