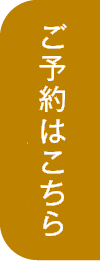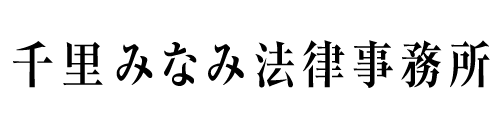【大阪の離婚弁護士が教える】父親が子の監護者に指定された事例①
裁判所において、親権・監護権が争いになった場合、現実的には父親が子どもの親権者・監護者に指定されることは稀です。
この傾向は、子どもが幼年の場合にはより顕著です。
では、いったいどのような場合に、父親が親権者・監護者に指定されるのでしょうか。
今回から数回に分けて、父親が監護者に指定された事例を紹介してみたいと思います。
【東京高裁平成24年10月5日決定】
1 本件事案の概要は、次のとおりである。
抗告人は、未成年者の母であり、相手方は未成年者の父である。抗告人と相手方は、結婚当時から静岡県に居住し、未成年者を出産後は、共稼ぎであったことから、育児を分担して未成年者を養育していたが、両者の将来設計についての意見の相違等から夫婦仲が悪化した。このような中で、抗告人は、平成23年10月3日、相手方の実家で養育されていた未成年者を強引に引き取って埼玉県の抗告人の実家に連れ帰って養育するに至った。これに対して相手方は、平成23年11月8日、未成年者の監護者を相手方と定め、未成年者の引渡しを求める審判の申立てをし、同日、審判前の仮の処分として子の引渡しを求める申立てをした。
原審は、当事者から提出された証拠のほか、家庭裁判所調査官の調査も経た上、平成24年5月10日、相手方の審判及び審判前の保全処分の申立てをいずれも認める審判をしたので、抗告人が抗告した。
平成24年5月24日、相手方の申立てによる審判前の保全処分の執行により、未成年者は、抗告人から相手方に引き渡され、現在は、相手方がその父母の助力を得て未成年者を養育している。未成年者は、現在4歳であり、保育園に通っている。
事実関係の詳細は、原審判「理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 上記のとおり、本件は、抗告人と相手方の不仲に端を発し、抗告人と相手方が共同して養育していた未成年者をめぐって、まず抗告人が相手方の実家から未成年者を強引に引き取って抗告人の実家に連れ帰って養育することとなり、これに対して相手方が審判前の仮の処分の執行により、未成年者の引渡しを受けて、養育しているものであり、未成年者の年齢が4歳であって、一般的には母親のもとで養育されるのが自然な年齢である。しかし、未成年者をめぐっては、原審判も認定するとおり、父子関係及び母子関係とも良好であり、未成年者にとって双方とも、よき父、よき母であることから、抗告人と相手方は不仲で、互いに遠隔の地に居住しており、いずれかを監護者と定める必要があるものの、その決定には慎重を要するものである。
そこで、当裁判所は、原審が当事者から提出された証拠のほか、家庭裁判所調査官の調査も経た上で審判をしたものではあるが、当審においても、再度家庭裁判所調査官による調査を実施し、審判前の保全処分の執行として未成年者の相手方への引渡しがされた後の状況もつぶさに見分することとして、家庭裁判所調査官2名に対して共同して調査するよう調査命令を発した。家庭裁判所調査官は、この命令に基づき、平成24年7月、当庁において抗告人及び相手方並びに抗告人の母と面接をし、同年8月、静岡県所在の相手方の実家に臨んで、未成年者、相手方の父母及び相手方と面接をして調査を実施し、同月29日、報告書を提出した。
この報告書において、特に注目すべきは、相手方及び相手方の父母とも、未成年者が抗告人及びその父母に養育されている期間中、しつけがきちんとされていたことを感じており、愛情と教育的配慮をもって育てられてきたと認められることであり、また、相手方及びその父母の養育も、家庭裁判所調査官からみて行き届いていると感じられることである。このような中で、抗告人と相手方のいずれを監護者と定めるかを決定することは、なかなか困難なことであるが、原審判が指摘するとおり、抗告人及び相手方の経済状態、抗告人の監護環境が突然形成されたものであること、抗告人と相手方の従来の監護の状況等からすれば、当裁判所も、原審同様、相手方を未成年者の監護者に指定するのが相当であると判断するものである。
3 抗告人の当審における主張に対する判断を付加すると、次のとおりである。
(1) 抗告人は、相手方と別居するまで、抗告人が未成年者の主たる監護者であり、適切に監護していたのに対し、相手方と未成年者の関係は決して良好と言えるものではなく、抗告人の妹や母も未成年者の監護に協力していたと主張する。しかし、抗告人と相手方が同居していた当時は共稼ぎをしており、勤務時間等の労働条件も同程度であり、乳児期はともかくとして、いずれかが主たる監護者であったといえるものではなかったところ、相手方の実家が近くであったことなどから、未成年者が発熱により保育園を休園したり、勤務の都合上双方の帰宅が遅くなるときなどには、同じ静岡県内に居住する相手方の父母の協力が得られていたことは、原審判の認定したとおりである。一件記録によれば、抗告人の妹や母が埼玉県から静岡県に来て未成年者の監護をしたことも認められるが、その内容及び頻度からみて、相手方の父母のかかわりの方がより深かったことを左右するものとはいえない。
(2) 抗告人は、未成年者を相手方実家から連れ出した際には、平穏に未成年者を受け取っており、力づくで未成年者を連れ出したものではなく、また、抗告人の埼玉県内の実家における未成年者の監護状況は、抗告人の母や妹の協力が得られ、医療環境、教育環境も優れ、抗告人の勤務状況も平成24年1月中旬以降安定しており、未成年者と良好な母子関係を継続しているから、このような現状を尊重すべきであると主張する。しかし、抗告人が相手方の実家の2階から未成年者を連れ出し、それまでの居住地であった静岡県から埼玉県内の抗告人の実家に未成年者を連れていった状況は、決して平穏なものではなく、未成年者の生活環境を急変させたものであって、配慮に欠けるものであったと評さざるを得ないものである。抗告人は埼玉県内の実家において、抗告人の妹や母の援助を受けながら未成年者を監護し安定した生活を送っていたことは認められるものの、上記のような経緯からみて、このことを過度に重視することは相当とはいえない。
(3) 抗告人は、相手方が監護者としての適格性を欠いており、その父母の協力状況にも不安があり、未成年者のしつけは不十分であるのに対し、未成年者は抗告人との面会交流においても良好な関係が保たれていた状況からみて、未成年者は精神的結びつきの強い抗告人の下で監護養育されるのが適当であると主張する。しかし、未成年者は、平成24年5月24日、保全処分に基づく強制執行により、相手方の監護下に移動したところ、当審家庭裁判所調査官の調査報告書によれば、未成年者の平日の日常的な監護や家事は、相手方の母親が中心となって行い、相手方の父親がそれを補っており、相手方は、平日の帰宅後や休日に未成年者と遊ぶことを中心としたかかわりを持っていること、住居の衛生面や室内の環境等についても未成年者の福祉を害するような問題はなく、未成年者は年齢相応の心身の発達を遂げており、相手方は未成年者のアトピーやぜんそく及び食事等について日常的に必要な配慮をしていること、未成年者は保育園での生活に適応し、楽しんでいること、強制執行により未成年者の保育環境を含む生活環境が変化したが、未成年者の情緒に不安定なところもなく、現在の未成年者の監護について子の福祉の観点から大きな問題点はなかったことが認められ、未成年者の現在の監護状況が安定したものであることからみても、抗告人の上記主張を採用することはできない。なお、未成年者は、抗告人との面会交流において親和性が保たれていたことがうかがわれ、このことは今後の抗告人と未成年者との母子関係を良好に保つために望ましいことであるが、このことをもって抗告人を監護者とすべきであるとまでいうことはできない。
これは、もともと母親と子どもが一緒に暮らしていたという状況下において、父親が監護者に指定された事例であることから、かなり稀な事例と思われます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。