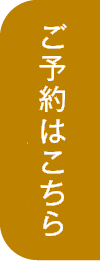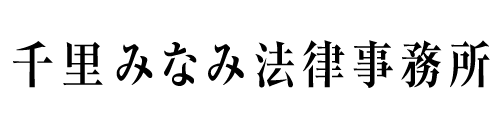【大阪の離婚弁護士が教える】父親への親権者変更を認めた事例④
以前の記事で、父親への親権者変更が認められた事例を紹介しましたが、今回はその第4弾です。
【東京家裁平成26年2月12日審判】
2 認定した事実
本件記録によれば,本件につき次の事実が認められる。
(1)申立人と相手方は,平成14年×月×日に婚姻し,同15年×月×日に未成年者C(以下「未成年者」という。)をもうけたが,平成20年×月×日,未成年者の親権者を相手方と定めて協議上の離婚をした(以下「本件離婚」という。)。
(2)相手方は,離婚に伴い未成年者とともに,申立人肩書住所地に所在するマンション(以下「申立人宅」という。)から○○に所在する相手方の実家(以下,単に「相手方実家」という。)に転居した。なお,相手方実家は,申立人宅と道路を挟んだ向かいに位置する。
(3)上記転居後,相手方は,未成年者のほか,相手方の父D,母E,姉F及び弟Gとともに相手方実家で生活した。しかし,次第に,相手方は同居する親族と不仲となり,対立が顕著となっていった。また,平成22年ないし同23年ころからは,未成年者への監護意欲が希薄となり,監護が疎かになっていったため,次第に姉Fを中心とする相手方の親族が未成年者の監護を担うようになっていった。
(4)以上の経緯を経て,平成24年×月×日,相手方は,その肩書住所地に所在する賃貸物件へ転居した。転居に際し,相手方は未成年者を伴おうとしたが,未成年者はこれを拒否し,相手方実家に留まった。
(5)現在,未成年者は○○の公立小学校の5年生であり,姉Fを中心とする相手方の親族による監護のもと相手方実家で生活している。そして,申立人とは,月に1回の頻度で週末にかけ申立人宅に宿泊するなどの交流が存するが,相手方との交流はほぼ途絶えている。
(6)申立人は映像制作会社に勤務し,約600万円の年収を得ている。他方,相手方は,事務職員としてデータ入力当の事務に従事しており,月収約15万円を得ている。
3 当裁判所の判断
前記2,(5)のとおり,未成年者は,姉Fを中心とする相手方親族による監護のもと,相手方実家で生活しているところ,本件記録に照らしても,未成年者の監護状況に問題点は見当たらない。そして,家庭裁判所調査官による平成25年×月×日付け調査報告書(以下「本件報告書」という。)によると,未成年者の実際の監護を担う姉Fを中心とする相手方親族と申立人との関係は良好であるのに対し,相手方親族と相手方との関係は良好でないことが確認できる。
しかも,本件報告書によれば,未成年者の相手方に対する印象・評価も良好でないことは否定し難い上,家庭裁判所調査官が未成年者に今後の生活等についての意向を尋ねたのに対しても,未成年者は,相手方と生活はしたくない旨及び現在の生活を続けたいし,また,将来的には,申立人宅に生活拠点を移転することになるであろうが,その場合にも相手方実家と行き来したい旨を述べている(このような未成年者の意向も,同人の年齢〔数か月後には11歳に達する小学校5年生である。〕や本件報告書から確認できる未成年者の応答ぶり等からすると,十分な判断のもとでの意思の表明として尊重するのが相当である。)。
してみると,本件離婚後,相手方の未成年者への関わりが変化し,しかも,相手方と未成年者が生活拠点を異にするなど,未成年者を巡る監護状況に変更が生じているため,その状況に応じて,未成年者の親権者を相手方から申立人へ変更する必要があると認められる。
この裁判例では、現状、親権者である母親と子が一緒に暮らしていないことや、小学5年生になろうとする子が母親との生活を拒否する意向を有していることなどを考慮して、父親への親権者変更を認めました。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。