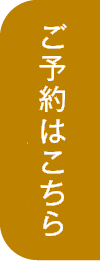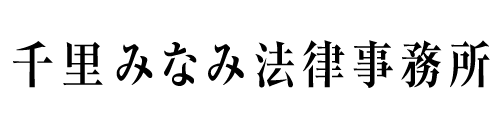【大阪の離婚弁護士が教える】父親が監護者に指定された事例④
【大阪高裁令和元年6月21日決定】
(1) 上記認定事実によれば、相手方は、本件別居までは未成年者の主たる監護者であり、その監護状況にも特段の問題はなく、今後、未成年者を監護する監護態勢も整っているといえる。
(2) 他方、未成年者が抗告人宅に戻った後の、抗告人による未成年者の監護状況にも特段の問題はなく、監護補助者である父方祖母は、77歳と高齢ではあるが健康であって、今後も監護補助を続けられる見込みである。
なお、未成年者はみずからの意思に基づいて抗告人宅に戻ったのであり、抗告人から不相当な働き掛けがあったことはうかがえないから、抗告人が未成年者の監護を開始したことが違法、不当とはいえない。また、原審がした審判前の保全処分に係る未成年者を相手方に仮に引き渡すことを命じる審判後も、抗告人が未成年者の監護を継続しているのは、未成年者が相手方に引き渡されることを強く拒んだために任意の引渡しができなかったためであるから、そのことをもって抗告人の監護が違法であるとか、監護者として不適格であるとまではいえない。
(3) また、未成年者は、本件別居前から抗告人との父子関係が良好であり、抗告人との同居の継続を強く求めている。他方、未成年者は、相手方に対する不信感等もあり、相手方との同居を拒んでいる(相手方との面会交流にも消極的である。)。
(4) さらに、未成年者と長女は、いずれも小学校6年生(11歳)であり、未成年者らの兄妹関係は既に良好に形成されている。また、抗告人宅と相手方宅は、いずれも未成年者らが通う小学校の校区内にあり、相互の距離も近く、未成年者と長女は自由に交流することができる。そうすると、未成年者と長女の監護者を抗告人と相手方に分離しても、既に形成されている兄妹間の心理的結び付きに大きな影響を与えるものではないから、未成年者らの福祉が害されることにはならない。
(5) 以上の未成年者の従前の監護状況、今後の監護態勢、未成年者と当事者双方との心理的結び付き、未成年者の心情等を総合すると、抗告人において未成年者を監護する方が、未成年者の心理的安定が保たれ、その健全な成長に資し、未成年者の福祉に適うものと認められる。また、未成年者は、相手方に引き取られることを強く拒んでおり、従前と同様、自ら抗告人宅に戻る可能性が高いから、相手方を未成年者の監護者に指定し、その引渡しを命ずることは相当ではない。
したがって、抗告人を未成年者の監護者と指定するのが相当である。そうすると、相手方を未成年者の監護者に指定することを前提とする子の引渡しの申立ては、理由がないから却下すべきである。」
2 よって、原審判中未成年者に関する部分は相当ではないからこれを取り消した上、抗告人を未成年者の監護者と指定し、相手方の子の引渡しに係る申立てを却下することとし、主文のとおり決定する。
子どもが自らの意思で父親宅に移り、父親との同居を強く求めているという事案において、父親が監護者に指定されました。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。