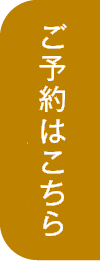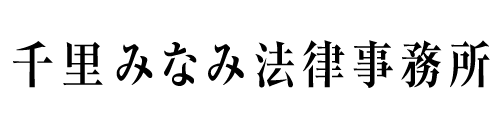【大阪の離婚弁護士が教える】有責配偶者からの離婚請求が認められるための別居期間とは?
前回の記事で、別居期間が32年にも及んでいるにもかかわらず、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった事例を紹介しました。
ですが、現在の実務においては、昭和62年に出された最高裁判例により、有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の要件を満たせば、離婚が認められるようになっています。
その要件の一つが、「相当長期間の別居」です。
最高裁昭和62年9月2日判決は、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいる場合には相当長期間の別居という要件をみたすと述べています。
ただ、これだけを読んでも具体的に何年なら相当の長期間なの?という疑問を持たれるはずです。
特に「当事者の年齢及び同居期間との対比において」という部分をどう解釈するのかという点がよく分からないところです。
当事者の年齢が若ければどうなの?その反対なら?などの疑問が湧いてきます。
ここで、このような疑問を解決するべくこの最高裁判決の解説(いわゆる「調査官解説」)を見てみることにします。
ここにいう別居期間は、有責配偶者からの請求の否定法理を排斥する要件として、前記のような有責性を含む諸事情から解放するに足りるものでなければならず、したがって、相当の長期間であることが必要である。別居期間が本件事案のように36年にも及ぶ場合はもとより、20年ないしは15年であっても、無条件に長期としてよいであろうが、10年にも満たないような場合には、同居期間や両当事者の年齢と対比して相当の長期間とはいえないと判断されることがありえよう。たとえば、両当事者が相当若年であるときは復元可能性にかんがみ相対的に長い期間が要求され、一方、同居期間が極めて短いようなときには比較的短くとも長期間と判断される場合があろう。また、この別居期間は、離婚要件としての明確を期すために、原則としてその理由などを問わずに事実審の口頭弁論終結時までの自然的時間の経過をいうものであるから、その期間には、調停前の別居期間はもちろん、調停期間、調停による別居期間、一、二審の審理期間も含まれることになり、事件によっては訴え提起時点では短い期間のこともありえよう。更にいえば、この期間は、婚姻の拘束力の弱化に伴い、あるいは社会の意識の変化に伴い、今後一層短くなるかもしれない。
この解説を前提とすると、若年夫婦や同居期間が長い夫婦の場合には相対的に長期間の別居期間が要求されると解することができそうです。
では、有責配偶者からの離婚請求が問題となった実際の裁判例において、どの程度の別居期間で離婚が認められているのか、あるいは認められていないのかという点を見てみたいと思います。
【離婚が認められた事例】
①同居期間4年、別居期間30年、子成人のケース(最高裁昭和62年11月24日判決)
②同居期間17年、別居期間22年、子成人のケース(最高裁昭和63年2月12日判決)
③同居期間21年、別居期間16年、子成人のケース(最高裁昭和63年4月7日判決)
④同居期間10カ月、別居期間10年3か月、子なしのケース(最高裁昭和63年12月8日判決)
⑤同居期間23年、別居期間8年、子成人のケース(最高裁平成元年3月28日判決)
⑥同居期間5年、別居期間15年6か月、子19歳のケース(最高裁平成元年9月7日判決)
⑦同居期間23年、別居期間8年、子成人のケース(最高裁平成2年11月8日判決)
⑧同居期間17年2か月、別居期間9年8か月、子成人のケース(最高裁平成5年11月2日判決)
⑨同居期間15年、別居期間13年11か月、子高校2年のケース(最高裁平成6年2月8日判決)
【離婚が認められなかった事例】
⑩同居期間6年7か月、別居期間2年4か月、子7歳のケース(最高裁平成16年11月18日判決)
⑪同居期間6年、別居期間13年、子高校3年と中学2年のケース(東京高裁平成9年11月19日判決)
⑫同居期間27年、別居期間7年数か月、子成人のケース(名古屋高裁平成15年2月21日判決)
⑬同居期間21年、別居期間9年、子成人のケース(福岡高裁平成16年8月26日判決)
⑭同居期間14年、別居期間9年以上、子は成人しているものの四肢麻痺の重い障害を有するケース(東京高裁平成19年2月27日判決)
裁判例を概観するとお分かりいただけるかと思いますが、上記の14件の裁判例の中では、別居期間が15年を超えるケースではいずれも離婚が認められています。
一方で、別居期間8年で離婚が認容されているケース(⑦のケース)があるのに対して、別居期間13年でも離婚が認容されないケース(⑪のケース)があるように、単純に別居期間の長短だけで結論が決まっているわけではないということには注意が必要です。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための3つの要件については、「これらの要件がそれぞれ充足すれば、それで有責配偶者による離婚請求が認められるという単純な判断構造を有するものではなく、これらの要件を充足するかどうかの分析とそれに関する各事情の認定をした上で、それらの各事情・評価を踏まえ、さらに信義則に照らして、有責配偶者の当該離婚請求が是認できるものであるのかという総合的な判断を行うという複合的構造を有するものと見ることができる。」との指摘(松原正明編著『人事訴訟の実務』276頁)や「単に期間の長短の問題ではなく当事者の別居中における態度の誠実さが読み込まれているようにも思われる。」といった指摘(右近健男『家族法判例百選〔第5版〕』33頁)もなされているところです。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。