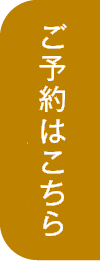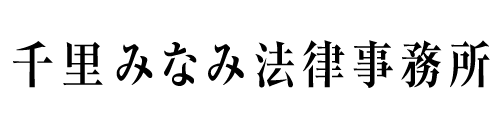【大阪の離婚弁護士が教える】父親(男性)が親権者・監護者になることができる場合とは?
1.はじめに
現行民法においては、父母のいずれかを親権者に定めなければ離婚することができません。
そのため、離婚に当たって親権が争いになれば、訴訟によって裁判官にいずれが親権者として妥当かを決めてもらうしかありません。
また、離婚前の別居時点でも、監護者をいずれにするかが争いになるケースもあります。
この場合も、いずれかが審判申立てをすれば、最終的には裁判官に監護者を決めてもらうことになります。
今後、共同親権制度が導入されることになりますが、当事者間で争いがある場合には共同親権か単独親権かを裁判官に決めてもらうことになりますし、たとえ共同親権となったとしても、必ずしも子どもと一緒に暮らすことが確約されるわけでもありません(共同親権については、こちらの記事を参照ください)。
そこで、今回はどのような場合に父親(男性)が親権者・監護者となるのかという点について解説をしてみたいと思います。
現行の単独親権制度を前提とした説明にはなりますが、今後導入される共同親権制度を考える上でも役に立つと思われます。
2.父親(男性)が親権者・監護者になる場合
夫婦の話し合いで、父親(夫)を親権者・監護者にすることに合意ができる場合、つまり母親(妻)が父親を親権者・監護者にすることに異存がない場合は、父親が親権者・監護者となることができます。
しかし、母親(妻)が異存があれば、前述のとおり、法的手続をとって決着をつけるほかありません。
そこで、以下では、法的手続において、父親が親権者・監護者となることが認められるのはどのような場合かという点について説明をしていくことにします(父母の話し合いで解決する場合は対象としていないということです)。
この点については、「実務上、母が監護者と定められる事案が圧倒的に多く、父が監護者と定められるのは、例外的な場合です。」といわれています(『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』131頁)。
では、どのような場合に例外的に父親が親権者・監護者と認められるのでしょうか。
同書は次のように説明しています。
例外的に、父が監護者と定められるのは、母が監護者と定められる場合の裏返しで類型化すると、①主たる監護者が父である場合、②主たる監護者は母であるが、母の監護態勢等に特段の問題がある場合、③主たる監護者は母であるが、小学生以上の子が、父お供に暮らすことを明確に希望しており、父の監護態勢が整っている場合であると考えられます。
また、年齢の高い子の監護者としての適格性は、子の意思尊重の基準により判断されることから、④小学校高学年以上の子が、父と共にに暮らすことを希望している場合にも、父が監護者と定められます。
(中略)当事者からは上記⑴②(母の監護態勢等に特段の問題がある)の主張がされることが多いですが、(中略)特段の問題が認められることはまれであり、(中略)母の精神状態や言動に一見して顕著な問題が認められる場合でなければ、当該主張が容れられることはありません。
(『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』131-134頁)
上記説明を見ていただくと、父親が親権者・監護者と認められるのは、実務上かなり稀であることが分かると思います。
3.父親が親権者・監護者と認められた裁判例
以下では、実際に父親が親権者・監護者と認められた裁判例をいくつか見てみたいと思います。
【大阪高決令和元年6月21日】
(1) 上記認定事実によれば,相手方は,本件別居までは未成年者の主たる監護者であり,その監護状況にも特段の問題はなく,今後,未成年者を監護する監護態勢も整っているといえる。
(2) 他方,未成年者が抗告人宅に戻った後の,抗告人による未成年者の監護状況にも特段の問題はなく,監護補助者である父方祖母は,77歳と高齢ではあるが健康であって,今後も監護補助を続けられる見込みである。
なお,未成年者はみずからの意思に基づいて抗告人宅に戻ったのであり,抗告人から不相当な働き掛けがあったことはうかがえないから,抗告人が未成年者の監護を開始したことが違法,不当とはいえない。また,原審がした審判前の保全処分に係る未成年者を相手方に仮に引き渡すことを命じる審判後も,抗告人が未成年者の監護を継続しているのは,未成年者が相手方に引き渡されることを強く拒んだために任意の引渡しができなかったためであるから,そのことをもって抗告人の監護が違法であるとか,監護者として不適格であるとまではいえない。
(3) また,未成年者は,本件別居前から抗告人との父子関係が良好であり,抗告人との同居の継続を強く求めている。他方,未成年者は,相手方に対する不信感等もあり,相手方との同居を拒んでいる(相手方との面会交流にも消極的である。)。
(4) さらに,未成年者と長女は,いずれも小学校6年生(11歳)であり,未成年者らの兄妹関係は既に良好に形成されている。また,抗告人宅と相手方宅は,いずれも未成年者らが通う小学校の校区内にあり,相互の距離も近く,未成年者と長女は自由に交流することができる。そうすると,未成年者と長女の監護者を抗告人と相手方に分離しても,既に形成されている兄妹間の心理的結び付きに大きな影響を与えるものではないから,未成年者らの福祉が害されることにはならない。
(5) 以上の未成年者の従前の監護状況,今後の監護態勢,未成年者と当事者双方との心理的結び付き,未成年者の心情等を総合すると,抗告人において未成年者を監護する方が,未成年者の心理的安定が保たれ,その健全な成長に資し,未成年者の福祉に適うものと認められる。また,未成年者は,相手方に引き取られることを強く拒んでおり,従前と同様,自ら抗告人宅に戻る可能性が高いから,相手方を未成年者の監護者に指定し,その引渡しを命ずることは相当ではない。
したがって,抗告人を未成年者の監護者と指定するのが相当である。そうすると,相手方を未成年者の監護者に指定することを前提とする子の引渡しの申立ては,理由がないから却下すべきである。
【福岡高決令和元年10月29日】
(1) 前記認定事実によれば,相手方は,G内に居住していた頃は,看護師として勤務しながら,家事と育児を全面的に担っており,平成23年9月にH内に転居した後も,抗告人の求職期間中の相手方の就労時間を除けば,抗告人がYに就職する平成27年11月頃までは,家事と育児を主として担っていたと認められる。しかし,相手方は,平成26年3月にP保育園を退職した後,頻繁に転職を繰り返すようになり,平成28年7月には抑うつ神経症の診断を受け,パチンコや貴金属の割賦購入,借入金の増加,他の男性との密接なやり取りもこうした時期に重なっていることからすると,抗告人がYに就職して安定的に育児に関与できるようになった頃には,相手方の精神状態は極めて不安定となっており,その監護能力も相当低下していたと考えられる。そのため,別居に至るまでの3年程度は,食事の準備を除けば,子らの監護を主として担っていたのは抗告人であったと推認される。
このような経緯からすると,同居中の子らの監護についての時間的ないし量的な実績は,相手方と抗告人とで明らかな差があるとはいえず,その時々の生活事情を踏まえて相補って監護していたのが実情と考えられるが,子らの乳児期に主として監護をしていたのが相手方であることや,子らの発言の中に,相手方への強い思慕を示す言葉が見られることからすると,子らは,相手方に対してより強い親和性を有していることが窺われる。
もっとも,相対的な親和性の強さをこのように理解したとしても,子らは抗告人とも良く親和していることに加え,物心ついた頃からHで生活し,原審判後には,二女もZ小学校に入学するとともに,フットベースチームにも入り,いずれについてもよく適応している。そして,抗告人は,相手方との別居後,子らの生活や学習の細部にわたって配慮し,その心身の安定に寄与していることから,抗告人の監護能力と子らとの関係に問題は見受けられないことに加え,現在は,相手方との宿泊付きの面会交流も安定的に実施されている状況にある。就学後の子らについて監護者を定めるに当たっては,従前からの安定した監護環境ないし生活環境を維持することによる利益を十分考慮する必要があり,乳幼児期の主たる監護者であった相手方との親和性を直ちに優先すべきとまではいえない。さらに,長女は,相手方との面会交流時にはEで相手方と暮らしたいと繰り返し発言しているが,担任教諭に対してはZ小学校や友人と離別することへの強い不安を訴えているのであって,相手方への上記発言が長女の相手方への思慕を示す表現であるとしても,本件監護者指定における位置付けについては慎重に評価・判断する必要がある(なお,二女は,調査官との面接時に,抗告人から怒られることやフットベースに参加することに不満を漏らしているが,その口調や表情から深刻さは感じ取れなかったとの調査官の意見もあることに加え,二女は,抗告人への親和性を示す発言もしており,現在もフットベースを継続していることからすると,その個々の発言に結論的な意味を持たせるべきではない。)。
以上の事情を考慮すれば,子らにとっては,現状の生活環境を維持した上で,相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うというべきであるから,子らの転居・転校を伴う相手方への監護者指定と子らの引渡しは相当ではない。
(2) これに対し,相手方は,子らが明示的に相手方との生活を希望していることや,抗告人から抑圧されて言いたいことが言えない状況にあること,抗告人が面会交流を妨害するような行動をしていることを指摘するが,前記のとおり,子らの年齢からすると,相手方と暮らしたいという発言は相手方への思慕を示す表現と解するにとどめるのが相当であり,その意思を考慮する際には,日常生活から窺われる現状への肯定的な心情をも含めて判断する必要がある。また,調査官調査の結果によれば,抗告人と子らの父子関係は良好に形成されており,子らが抑圧された環境に置かれているとは認められないし,面会交流については,当事者双方に感情的な対立はありながら,H・E間の宿泊付きの面会交流を任意に実施することができており,子らも後ろめたさを感じることなく楽しんで過ごしていることからすると,抗告人の対応が監護者として不適切ということはない。
したがって,相手方の指摘する事情を考慮しても,前記の判断を覆すには至らない。
【名古屋高決令和2年6月9日】
抗告人(昭和56年×月〇日生)と相手方(昭和52年×月〇日)は、平成20年12月10日に婚姻した夫婦であり、平成25年×月〇日に未成年者である長女C(以下「長女」という。)をもうけた。抗告人は、婚姻後、相手方や相手方親族への不満等に起因するストレスによる不調を訴える中で、相手方や相手方家族が死ねばいいと口走ったり、相手方に度々離婚を要求したり、長女を置いて出て行くと口にすることがあり、抗告人の言動は平成30年12月頃から更にエスカレートした。抗告人と相手方は、令和元年5月5日夜、〇〇県○○所在の自宅(相手方宅)において、相手方父母や相手方の妹家族と相手方実家で食事をしたことについて口論となり、怒りが収まらなかった抗告人は、相手方の部屋に押し掛けたが、話合いにならなかったため、台所から包丁を持ち出した。これを見た相手方は、抗告人との婚姻生活の継続を諦め、離婚を覚悟し、抗告人に伝えた。翌6日、抗告人と相手方、相手方父、抗告人母で話合いをしたが、抗告人は離婚に応じず、長女に会いたいと取り乱し、話がまとまらないまま夜遅くになって話合いは打ち切られた。相手方母は、先に長女を相手方実家へ連れて帰っており、相手方は、相手方実家に転居することを決め、抗告人を残して相手方宅を出た。同日以降、抗告人と相手方は別居し、相手方は相手方実家において相手方両親の援助を受けながら長女を監護している。(中略)
抗告人は、原審判は抗告人が精神的に不安定になった末に刃物を持ち出したことを過大に重視しているが、将来的に抗告人が相手方と離婚することは確実であり、今後は抗告人にストレスが生じることはあり得ず、抗告人は精神的に安定していることから、抗告人の刃物持出し行為を過大視した原審判は不当であると主張する。
しかしながら、抗告人が相手方と離婚した後も何らかの原因により精神的なストレスを抱え、それに伴って危険な行為に及ぶ可能性も否定することはできないから、抗告人の上記主張は採用することができない。
【東京高決令和2年2月18日】
2 長女の監護者について
(1) 引用に係る第1事件の原審判「理由」第3の1の認定事実(以下,単に「認定事実」という。)(2)及び(4)(いずれも補正後のもの)のとおり,長女の従前の主たる監護者は抗告人であったと認められるものの,抗告人に別居先に連れて行かれた長女は,その翌日,自らの意思で相手方宅に戻り,その後,現在までの2年弱にわたって,相手方に監護されていることが認められる。そして,長女は,家庭裁判所調査官に対し,抗告人の異性関係についての不信感や,同居中の抗告人の生活態度等についての不満を述べたりしながら,抗告人との同居生活を拒否する意向を示しているところ,上記の長女の行動内容も併せ考慮すると,長女の上記意向は真摯なものと認められるし,現在,11歳という長女の年齢にも照らすと,その意向は,一定程度尊重すべきものである。
また,相手方の下での長女の監護状況を見るに,相手方は,仕事のために,平日や土曜日の日中は不在にしており,また,宿泊を伴う出張もあるものの,相手方の父母が中心となって監護補助に当たっており,家庭裁判所調査官による調査の結果を踏まえても,その監護態勢に具体的な問題は見当たらない(認定事実(6)(補正後のもの)参照)。当審において提出を求めた資料を精査した結果,長女の生活態度等に若干不安定な部分がうかがえるものの,相手方は,それに適切に対処しており(認定事実(9)(補正後のもの)参照),格別問題視すべき状況にあると評価することはできない。
以上によれば,別居前の長女の主たる監護者が抗告人であったことを考慮しても,現時点においては,長女の監護者を相手方と定めるのが相当である。
(2) これに対し,抗告人は,前記第2の2(2)のとおり,①別居までの長期間の監護の実績があること,②長女の発言が相手方の影響を受けたものであること,③相手方が連日,長女を放置して女性宅に宿泊していること等を理由として,長女の監護者を抗告人と定めるべきである旨主張する。
しかし,長女の出生後,別居するまでの監護の実績は,監護者を定めるに当たっての重要な考慮要素ではあるものの,本件においては,前記(1)で説示したとおり,長女が,自ら抗告人の下を離れて相手方宅に戻り,その後,2年弱もの間,相手方が長女を監護しているといった事情こそを重視すべきである。そして,抗告人と相手方がそれぞれ他方の不貞行為を疑って探偵会社に素行調査を依頼するといった状況にあること等からすると,長女が両親の対立の影響を受けている可能性は否定し得ないものの,長女は,抗告人に別居先に連れて行かれた直後の時点で,自らの意思で,相手方の下に戻る意向を抗告人に伝えているのであるから,それが相手方の影響によるものであったとは考え難いし,その後,抗告人と長女が面会する機会がそれ相応にあった中でも,長女の意向が変化したことはうかがえず,引き続き相手方宅での生活を選択し続けていることからすると,長女の上記意向は,自らの考えに基づく部分が大きいというべきである。また,相手方が長女を放置して女性宅に宿泊しているといった事実を認めるに足りる資料は存在せず,審理終結の直前に抗告人から提出された調査報告書(乙40)が,相手方が長女を連れて女性宅に宿泊した事実を示すものであるとしても,その経緯等は判然としないから,仮に,そのような事実があったとしても直ちに相手方が長女の監護者としての適格性を欠くということにもならない。
したがって,抗告人の上記主張を採用することはできない。
個々の事実関係は千差万別ですが、上記で紹介した裁判例はいずれも父親と子どもが一緒に暮らしていた(父親が同居親であった)という共通点があるといえます。
ただし、父親が子どもと一緒に暮らしていても、母親が親権者・監護者に定められる事例(母親の監護者指定・子の引渡し請求を認容する事例)も多々あり、やはり前述のとおり、父親が親権者・監護者として認められる事例は稀で、相応にハードルが高いというのが実情といえます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。