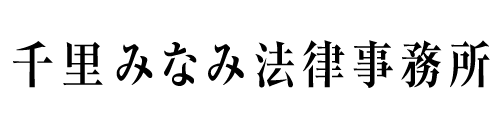【大阪の離婚弁護士が教える】離婚前の誓約書の効力~将来離婚することやその場合の条件を定めることは有効か?~
1.はじめに
将来離婚することを約束したり、将来離婚するとなった場合にはこのような条件で離婚をしようという合意をしたりしようとお考えの方もおられるかもしれません。
では、このような合意は有効なのでしょうか。
ネット上の記事を見てみいると、やや錯綜しているように思われますので、整理してみたいと思います。
2.将来離婚するとの合意の有効性
たとえば、「〇年後に離婚する」とか「子どもが大学を卒業したら離婚する」というような合意をしたとします。
当事者がこのような合意に基づいて、実際にそのとおりに離婚するのであれば問題ありません。
しかし、夫婦の一方がやはり離婚したくないと思った場合でも、このような離婚予約の合意に基づいて離婚届を提出する義務を負うのでしょうか。
この点に関しては、協議離婚は離婚届の届出によって成立するところ、離婚意思の合致は、離婚届の届出の時に存しなければならないため、離婚の予約は法律上無効であると考えられています(『新版注釈民法(22)親族(2)』17頁)。
裁判例を見てみても、「定められた金員を支払えば、原被告のいずれからも離婚を申し出ることができ、他方、その申し出があれば、当然相手方が協議離婚に応じなければならない」とする趣旨の誓約書の効力について、「本件誓約書は、将来、離婚という身分関係を金員の支払によって決するものと解されるから、公序良俗に反し、無効と解すべきである。」と判示しているものがあります(東京地判平成15年9月26日)。
また「身分行為として意思の自由が尊重される離婚にあつては、右公正証書により離婚手続の履行を求めることができないことは明らかであり、右公正証書による離婚の合意は離婚の予約としての効力を有するにすぎない。」とした裁判例もあります(宮崎地判昭和58年11月29日)。
したがって、将来離婚するいった合意をしたとしても、その合意に基づき離婚届を提出する義務を負わせることはできないと考えられます。
ただし、このような合意をしたにもかかわらず、一方の配偶者がやはり離婚はしたくないと言い出した場合、話し合いによる解決はできないため、最終的には訴訟に至ることが考えられますが、その場合には離婚の予約の存在やその不遵守といった事情が斟酌される可能性が指摘されています(『新版注釈民法(22)親族(2)』17頁)。
以上をまとめると、
①将来的に離婚することを約束することは、当事者がそれに基づいて実際に離婚する際には意味がある。
②しかし、一方配偶者がその合意に反して、離婚したくないと言い出した場合には、法的には有効な合意とはいえず、その合意に基づいて離婚届を提出させる義務を負わせることはできない。
③ただし、最終的に訴訟に至った場合には、離婚予約の合意をしたこと自体が斟酌されて離婚が認められやすくなる可能性がある
ということがいえそうです。
3.将来離婚する際の条件を合意することの有効性
次に、将来離婚することになったときにはこのような条件で離婚しようという合意はどうでしょうか。
この点に関しては、大正時代の判例(大判大正6年9月6日)があります。
これは、将来夫より不和を醸し離婚する際には夫から妻に対し一定の金銭を交付する約束をしていたところ、いざ離婚となったのでその合意に基づいて妻が夫に対して金銭を請求したという事案ですが、裁判所は、このような約束は善良の風俗に反するものとはいえない(有効である)と判示しました。
したがって、将来の離婚条件の合意は直ちに無効となるものではないと考えられます。
その内容が公序良俗に反せず、かつ不当に離婚の自由を妨げない限り、有効と見るべきであるとの意見もあるところです(『新版注釈民法(22)親族(2)』17頁)。
また、財産分与に関してですが、「離婚前の財産分与契約は、内容が妥当であれば有効である。」と明記する文献もあります(『離婚判例ガイド[第3版]』134頁)。
もっとも、裁判例を見てみると、当事者間で合意した条件どおりに離婚できない場合もあるといえそうです。
先ほども挙げた東京地判平成15年9月26日を詳細に見てみることとします。
これは、夫婦が婚姻する際に次のような誓約書を取り交わした事案です(甲が妻、乙が夫)。
将来甲乙お互いにいずれか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚することが出来る。
(一) 甲の申し出によって協議離婚した場合は左記の条件に従い乙より財産の分与を受け、それ以外の一切の経済的要求はしない。
(イ) 婚姻の日より五年未満の場合 現金にて五阡万円
(ロ) 右同文 十年未満の場合 現金にて壱億円
(ハ) 右同文 十年以上の場合 現金にて貳億円
(二) 尚、乙の申し出によって協議離婚した場合は前項、第(一)項の金額の倍額とす
この事案において、夫が妻に対して離婚を求め、訴訟を提起しました(以下でいう「原告」は夫、「被告」は妻を指す)。
夫(原告)は、「本件誓約書は被告の意思に基づいて成立したものであるが、本件は協議離婚でなく、裁判離婚であるから、原告が離婚を求め、協議離婚が成立した際に支払うべき4億円も、被告が離婚を求め、協議離婚が成立した際の2億円も支払うべき義務はない。」とし、仮に2億円ないし4億円以上の財産分与が相当と判断される場合においては、予備的に「本件誓約書の趣旨は、協議離婚が整った場合、或いは、協議離婚が整わなかった場合には、裁判離婚等が成立した場合の財産分与額を定めるものと解すべきである。」と主張しました。
その上で、夫は、夫の財産は自己の才覚によって増加させたものであって、その財産形成に妻は寄与していないとして、財産分与は発生しない、仮に、財産分与が認められるとしても、離婚を最初に申し入れたのは被告であるから、本件誓約書による合意があることからすると、2億円を超える財産分与は認められないと主張しました。
これに対して、妻(被告)は概要次のように主張しました。
「本件誓約書第1項柱書の文言は、金銭の支払を条件に、いずれか一方の申し出によって、自由に離婚することを認めた規定であるから、明らかに一方当事者の意思表示に基づく離婚を想定しており、日本法で認められた、協議離婚、調停離婚、審判離婚、ないし裁判離婚のいずれの要件も充たさないものであるから、強行法規ないし公序良俗に反し、無効である。
本件誓約書は、220億円を超える共有財産に比して分与額が著しく低額であり、原告が有責である事案であることも鑑みると、相続の場合等に比しても不当であること及び相続契約をその内容に含んでいることからして、公序良俗に反し無効である。(中略)
本件誓約書が有効であったとしても、協議離婚の場合に適用があると解すべきであって、裁判離婚が問題となっている本件においては、適用がないと解すべきである。」
その上で、妻は、財産分与として少なくとも110億円の支払いを求めると主張しました。
さて、このような両者の主張を踏まえて、裁判所はどのように判断したかというと、まず誓約書の効力については、「仮に、本件誓約書を離婚が定まった場合の財産分与額を定めたものと解する解釈が可能で、かつ、他の無効事由が認められないとしても、本件誓約書は、文言上、協議離婚しか想定されておらず(中略)裁判離婚が問題となっている本件においては、効力はない。」と判示しました。
つまり、誓約書は協議離婚を想定したものであったため、訴訟にまで至っている以上、その効力はないと判断したわけです。
翻って、誓約書に「協議離婚」という文言がなかった場合にどのような判断がなされたのかは気になるところです。
結論についても触れておくと、最終的には裁判所は「原被告の婚姻が破綻したのは、主として原告の責任によるものであること、被告の経歴からして、職業に携わることは期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮にいれると、財産分与額は、共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円を相当と認める。」との判断を下しました。
上記裁判例は金銭的なことが問題となった事案ですが、親権など子どもに関する条件の場合はどうでしょうか。
この点、先ほども挙げた裁判例(宮崎地判昭和58年11月29日)において「本件離婚に伴う未成年者の親権者指定につき検討するに、前記認定のごとく、別居後長男啓充は原告が扶養していること、本件公正証書によつても原告が親権者となることが予定されていたこと等諸般の事情を考慮すれば長男啓充の親権者は原告と定めるのが相当である。」と判示されています。
このように、親権者を決めるに当たって、事前の合意内容が考慮されていることが分かります。
その一方で、事前の合意内容だけをもって親権者を決めていないということも分かります。
また、監護者指定の事件ではありますが、次のように判示した裁判例もあります(東京高決令和元年12月10日)。
本件親権者指定条項は,当事者が将来離婚する場合の未成年者の親権について定めたものであるが,その他の本件示談書中の各条項がいずれも婚姻関係の継続を前提にする内容であることに照らすと,当事者が本件親権者指定条項を合意するに当たり,具体的かつ現実的に離婚することを想定していたものとは認められない。また,本件示談の締結に際しては,代理人間の交渉が行われたとはいえ,同交渉の期間は抗告人の身柄拘束中の短期間にとどまることや,当事者が従前から離婚する場合の未成年者の親権について協議を行っていたこともうかがわれないことからすれば,本件親権者指定条項が,未成年者の利益等に配慮した十分な協議を経た上で合意されたものとも認め難いというべきである。
もとより子の監護者の指定に当たっては,子の利益の確保の観点から,従前の監護状況,現在の監護状況や父母である当事者双方の監護能力,子の年齢,心身の発育状況等の事情を実質的に比較考量して父母のいずれが監護者として適格であるかが検討されるべきものであるところ,これらについて慎重かつ十分な検討が行われたと認めるに足りる資料はない。
これらのことに照らすと,本件親権者指定条項は,将来離婚する場合の親権者の指定に際して重要な考慮要素となり得るものということはできるが,それを超えて,当事者が別居する場合に相手方が未成年者の監護を行う旨の合意を当然に含むものと解することはできず,また,未成年者の監護者の指定及びその引渡しの当否の判断において,上記のような経緯で合意された本件親権者指定条項の存在を殊更に重視することも相当でないというべきである。
この裁判例は、離婚前の監護者指定事件であるため、離婚時の親権者を決める離婚訴訟ではありませんが、参考になると思われます。
当事者間の話し合いにより離婚するのであれば(協議離婚・調停離婚)、事前の合意内容に沿って親権者を決めるということもあると思いますが、訴訟となった場合には、上記判示内容からすると、将来離婚する際の親権者指定の合意は、考慮要素とはなるものの、必ずしもその合意のみで親権者を決めるものではないと考えられます。
実際、この監護者指定の事件においては、親権を夫にするという親権者指定条項があったものの、監護権者を妻とするといった結論になっています。
以上をまとめると、
①将来の離婚の際の条件について事前に合意することは、その内容が公序良俗に反せず、かつ不当に離婚の自由を妨げない限り、有効と考えられる
②しかし、訴訟によって裁判所が離婚について判断する際には、その合意の内容次第では、合意どおりにならない可能性がある(とはいえ、考慮される余地はある)
ということがいえそうです。
4.民法754条との関係
民法754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と規定しています。
とすれば、いくら将来の離婚の予約や将来離婚する際の条件を合意していたとしても、いつでも取り消すことができるのではないかという疑問が出てきます。
この点については、婚姻関係が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、民法754条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないとした判例(最判昭和42年2月2日)があります。
したがって、婚姻関係が破綻した後であれば、夫婦間の合意は取り消すことはできないと考えられます。
また、民法754条による夫婦間の契約取消権の立法趣旨は、円満な婚姻生活の継続的維持のためにあるのであるから、それを前提としない離婚のための贈与契約や財産分与の協議(契約)の取消には適用ないものと解すべきであるとの意見もあるところです(『新版注釈民法(21)親族(1)』389頁)。
☆婚前契約・夫婦財産契約についてお知りになられたい場合は、こちらの記事を参照ください。