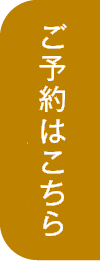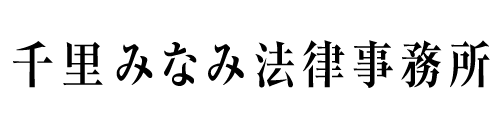【大阪の離婚弁護士が教える】家裁調査官が訴えられることがあるのか?
前回の記事で、家裁調査官の役割を紹介しました。
ただ、事件に関与してくれる家裁調査官の対応に対して当事者が不満を持つということがあります。
その結果、家裁調査官に対して国家賠償請求をするという発想になる人もいるかもしれません。
では、当事者が家裁調査官を訴えたという実際の裁判例(東京地判平成29年2月16日)を一つ見てみたいと思います。
【事案の概要】
原告が、妻の監護する子らとの面会交流に関する家事審判事件に関して家裁調査官の作成した調査の範囲・手法には不十分又は不適切な部分などがあるため、これにより原告は暴力を振るう人間であるという誤ったイメージを不当に作出されたとして、被告国に対し損害賠償を求めた事案。
【裁判所の判断】
家裁調査官は,人間関係諸科学の分野に関する専門的知識及び技法を有しており,家裁調査官による事実の調査は,そのような専門的知識を活用して行われることを予定したものであるから(平成24年最高裁規則第9号による廃止前の家事審判規則7条の3),本件面会交流申立事件のような平成23年法律第53号による廃止前の家事審判法9条1項乙類所定の家事審判事件に関する具体的な調査方法(調査の範囲及び手法)についてはその裁量に委ねられると解される。また,家裁調査官の調査は,家庭裁判所にその審判の資料を提供するために行われ,家事審判官がこれを参考にして審判を行うことになるところ,当事者は,家裁調査官の具体的な調査方法や報告内容に不十分又は不合理な部分があると考える場合には,家事審判手続において,家裁調査官の調査の成果物である調査報告書が信用性を欠くことを明らかにして調査の不備について不服を述べる機会があることが通常であるから,家裁調査官には具体的な調査方法のみならず調査結果についての意見の作成についても裁量が認められ,これを逸脱した場合あるいは濫用した場合に限って違法となるというべきである。
(2) 以上を踏まえて原告の個々の主張について検討する。
ア 原告は,本件調査官らが,原告希望者らへの事情聴取を全く行わないという不平等な調査を行ったと主張する。
しかしながら,前提事実によれば,本件調査は,家事審判官から「子の意向及び生活状況」についての部分調査を命じられて(本件調査命令)行ったものであることが認められ,そのような調査目的を達するためにどのような者を調査対象とするかの選択は家裁調査官の裁量に委ねられていると解されるから,原告希望者らへの事情聴取を行わなかったからといって本件調査官らに調査の範囲及び手法に関する裁量の逸脱あるいは濫用があるとはいえない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
イ 原告は,本件調査官らは,原告と本件未成年者らの交流が完全に遮断され,同人らが原告の悪口を言うDの影響を受けた状態であったので,このような状態を改善してから調査を行うべきなのに,これを改善しないまま調査をするという不平等かつ不適切な調査を行ったと主張する。
しかしながら,上記認定のとおり,本件調査の調査事項は「子の意向及び生活状況」であるところ,前提事実及び証拠(甲2)によれば,本件調査官らは,本件調査において,D宅及び土浦支部において各1回ずつ本件未成年者らと面接しているところ,いずれもDに席を外させて本件未成年者らのみの状態で面接していることが認められるのであり,Dの影響を受けない状態においても本件未成年者らの意向を確認しているから,本件調査に裁量の逸脱あるいは濫用があるとは認められない。原告主張の「このような状態を改善してから調査を行うべき」とする趣旨は必ずしも明らかではないが,本件調査官らに対して,原告と本件未成年者らとの関係を改善した上で本件未成年者らと面接すべきとするものであるとすると,相当な困難を求めるものであって到底採用できない。
ウ 原告は,本件二男に「どんな父ちゃんなら会ってもいい?」という質問をして,原告と会わないことが悪いことではないことを暗示したと主張する。
しかしながら,質問内容の適否の判断については,前記のとおり,家裁調査官の裁量に委ねられているから,本件家裁調査官らが本件二男に対し,「どんな父ちゃんなら会ってもいい?」という質問を控えるべき法的義務を原告に対して負っていたとはいえず,裁量を逸脱又は濫用したものとはいえない。また,証拠(甲2)によれば,上記質問は,本件二男が原告を恐がっており,学校に2度と来てもらいたくないなど,面会交流に否定的な発言がされたことを踏まえてされたもので,原告との今後の面会交流の方策を模索するために行われたものと解されるのであって,この質問が本件二男に対して原告と会わないことが悪いことではないことを暗示したものと認めること自体も困難である。そうすると,本件調査官らに裁量の逸脱あるいは濫用は認められず,原告の上記主張はいずれにしても採用できない。
エ 原告は,本件長男の出生地は〇〇であるのに,本件調査報告書に「△△において出生した」と記載したと主張し,確かに,前提事実によれば,本件長男は〇〇において出生したにもかかわらず,本件調査報告書には△△において出生した旨記載があることが認められる。
しかしながら,上記記載は,本件調査報告書のDの陳述要旨欄に記載されているものであり,実際にDが本件長男は△△において出生した旨説明をしたのであれば,本件調査官らは,Dの説明内容が正しいか否かにかかわらず,Dの説明をそのまま記載すべきであるから,Dの陳述内容に誤りがあることをもって本件調査官らが不適切な調査を行ったとはいえず,原告の上記主張は採用できない。
オ 原告は,本件調査官らは,本件調査報告書17ないし18頁において,本件長男は「叩かれた」という表現を使っているのに,同報告書21頁の「調査官の意見」欄では「暴力をふるわれたりした」との言い換えをして,原告が暴力を振るう人物であるというイメージを不当に作出したと主張する。
しかしながら,証拠(甲2)によれば,本件長男は,本件調査官らに対し,小学2年生頃から剣道の練習が始まり,練習中,原告から防具をつけない状態で竹刀や木刀で頭を叩かれたことがあり,頭部に腫れや顔面にあざが生じたり防具をつけていない左手を竹刀で叩かれたこともあったことやスキー場のリフトの乗り方や英語を教わる際にも原告から叩かれて何をやるにしても叩かれた旨説明したことが認められ,これらの事実に照らすと,本件調査報告書の「調査官の意見」欄に本件長男の意向として「暴力をふるわれたりした」と記載したことは,本件長男の面接調査の結果に基づくものであることが明らかである。
以上の事実からすれば,本件調査官らが本件長男の意向として原告から暴力を振るわれたりした旨を本件調査報告書に記載することは十分な理由があるもので裁量の逸脱あるいは濫用があるとは認められないから,原告の主張は採用できない。
(3) まとめ
したがって,原告が主張する本件調査官らの本件調査及び本件調査報告書の記載について,国家賠償法上違法であると認めることはできないから,原告の主張は理由がない。
ということで、この事件では、原告の主張は全て排斥され、国家賠償請求は認められないという結論になりました。
家裁調査官の作成した調査報告書等を見て、当事者が不満を抱くことがありますが、それに対して国家賠償請求が認められるということは現実的には困難といえそうです。
調査報告書に誤り等がある場合には、当該法的手続内における主張書面等でその点を指摘するというのが現実的な対応といえるのではないでしょうか。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。