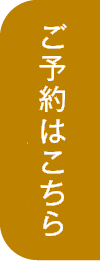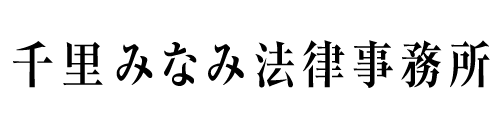【大阪の離婚弁護士が教える】完全解説・面会交流の間接強制事件の流れ
1.はじめに
今回は専門家向けの記事です。
したがって、用語の説明などは割愛したうえで、以下では面会交流の間接強制事件の一連の流れを説明していきたいと思います。
2.まずは3要件を満たす債務名義が必要
間接強制の申立てをするためには、まずは面会交流の間接強制が認められるための3要件を満たした債務名義が必要です(専門家向けの記事ですので、3要件の詳細は割愛します)。
別居親側からすれば、3要件を満たす債務名義がなければ、いくら面会交流が実施できないと訴えたとしても、間接強制をすることはできません。
この場合には、面会交流調停を申し立てるか、金銭的な請求でいうと慰謝料請求をすることが考えられます。
同居親側からすれば、3要件を満たす債務名義があるにもかかわらず、面会交流が実施されていないとすれば、別居親側から間接強制の申立てをされる可能性があると認識しておく必要があります。
3.間接強制の申立て
別居親側が、3要件を満たす債務名義に基づいて間接強制を申し立てる場合、調停又は審判等により面会交流を認めた家庭裁判所に申し立てをする必要があります(民事執行法172条6項・171条2項)。
間接強制の申立てがあると、裁判所は同居親がすべき給付の内容が特定されているかなどの強制執行の要件を審査し、その要件を満たす場合には、債務者(同居親)を審尋し(民事執行法172条3項)、間接強制決定するか否かが判断されます。
債務者の審尋は、書面で行われるのが通常だと思われます。
それゆえ、別居親側から間接強制の申立てがあると、裁判所から同居親に宛てて、間接強制の申立てがされたことを伝えるとともに、何か意見があるのであれば、書面を出すように求める旨の書面(審尋書)が届くのが通常です。
書面の提出期限については法定されていませんが、裁判所からは期限を切られるのが通常ではないかと思われます(大阪家裁の場合は、審尋書書が到達した日から14日以内とされているようです)。
ちなみに、東京地裁民事第21部の説明によると、「回答期限を10日として,債務者に対して,書面審尋(債務者の意見等を書面の提出により確認する手続)を実施しています。この期間中に,債務者から何も書面の提出がなければ,期限経過後に申立てを認容する決定がされます。債務者から書面が提出された場合には,かかる書面に対する反論等を求める場合があります。」と説明されています。
4.間接強制の審理・決定
同居親側が、子どもが拒否しているので、間接強制は認められるべきではないと主張することがあります。
この点に関しては、間接強制の3要件を示した最決平成25年3月28日は「子の面会交流に係る審判は,子の心情等を踏まえた上でされているといえる。したがって,監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判がされた場合,子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは,これをもって,上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し,又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別,上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。」と判示しています。
ただし、同調査官解説においては、「間接強制決定は、一般に、債務者が債務を履行することができることを前提としているといえる。本決定は、本件で問題となった子の心情については、間接強制決定の申立ての手続きで審理することができないとしたが、同手続において、債務者が債務を履行することができないか否かを審理することが一切許されない趣旨を示したとまではいえないと解される(本件は、子も比較的幼少で、(監護親の意思のみによって面会交流を実現することが可能であるとの判断を前提としてされたと解される)審判時から間接強制申立までの時間的な間隔も小さかった。)。」と記載されています。
現に、未成年者(15歳)が面会交流を拒否する意思を強固に形成しているとして、間接強制の申立てを却下した裁判例も存在するところです(大阪高決平成29年4月28日)。
審理の結果、間接強制決定をする場合には、債務者(同居親)に対して、一定期間内に調停調書又は審判で定められた面会交流を実施しなければ、面会交流の不履行1回当たり一定額の間接強制金を債権者(別居親)に支払うことが命じられます。
一方で、間接強制を認めない場合には、申立ては却下されることになります。
5.執行抗告
第1審の決定に対して不服がある当事者は、執行抗告をすることができます(民事執行法172条5項)。
執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければなりません(同法10条2項)。
また、抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から1週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければなりません(同法10条3項)。
執行抗告をする場合、上記のとおり、かなりタイトなスケジュールとなることには注意が必要です。
一方当事者から、執行抗告がされてから一定期間が経つと、高等裁判所から他方当事者に対して、執行抗告状(副本)や執行抗告理由書(副本)等が送付されるとともに、反論の書面等を提出するよう求める書面が届くのが通常です。
そして、双方の主張反論の後、高等裁判所が決定を出すことになります。
6.特別抗告・許可抗告
執行抗告に対して不服がある場合は、特別抗告・許可抗告をすることが可能です(民事執行法20条、民事訴訟法336条・337条)。
特別抗告の提起、許可抗告の申立て、いずれも高等裁判所の決定の通知を受けてから5日間の不変期間内に行う必要があります(民事訴訟法336条2項、337条6項)。
特別抗告については、理由の記載が抗告状にないときは、抗告人は、特別抗告提起通知書の送達を受けた日から14日以内に(民訴規則210条)、抗告理由書を原裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法336条3項、315条)。
許可抗告については、申立書に申立ての理由を記載しなかったときは、抗告許可申立て通知書の送達を受けた日から14日以内に(民訴規則210条2項)、理由書を原裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法337条6項、315条、民訴規則210条2項による同条1項の準用)。
なお、特別抗告、許可抗告いずれも執行停止効はないため、特別抗告の提起や許可抗告の申立てがされたとしても、高等裁判所の決定に基づく強制執行をすることは可能です。
7.強制金の取り立て
間接強制が認められる場合、その主文には「本決定の送達日以降、前項の義務を履行しないときは、不履行1回につき〇円の割合による金員を支払え」という趣旨の記載がなされます。
つまり、決定の送達日以降に、面会交流義務の不履行があれば、債権者(別居親)は、決定主文で認められた間接強制金の取り立てができることになります(翻って、決定の送達日以前に面会交流義務の不履行があったとしても、以前の分の間接強制金の取り立てを行うことはできません)。
具体的には、強制金決定によって債務者は金銭給付義務を負うことになるので、債務者が強制金決定に含まれる履行命令に違反したときは,債権者は、強制金決定を債務名義として(民事執行法22条3号)、条件成就執行文(補充執行文)の付与を受けて(同27条1項)、金銭執行の方法により金銭を取り立てることができ、履行命令の違反は、債務者が証明すべき事項であるが、民執法177条3項を類推して、裁判所書記官は、債務者に対し、一定の期間を定めて、履行の事実を証明する文書の提出を催告すべきであると解されています(『民事執行・民事保全法〔第2版〕(LEGAL QUEST)』有斐閣268頁)。
東京地裁民事第21部の説明によると「債権者が,間接強制決定に基づき,間接強制制裁金の取得実現のために債務者に対する強制執行を申し立てる場合には,一般的には,強制執行申立書のほかに,執行文を付与した間接強制決定正本・同決定の送達証明書を執行裁判所に提出する必要があります。」とされています。
8.請求異議訴訟
別居親から強制金の取り立てがされた場合、同居親は請求異議訴訟を提起して争うことができるのでしょうか。
この点、前掲調査官解説では「請求異議訴訟によって、監護親が義務を免れることになる場合があることを指摘する学説、裁判例があった。もっとも、どのような事由について、どのような根拠に基づき、どの債務名義に対する請求異議事由となるかについては更なる議論の深まりが期待される」と説明されるにとどまっています。
平成25年最決が請求異議訴訟に言及しなかったことについては、その読み方には議論が分かれるとして、「抗告人が主張しなかったために言及しなかったという理解もありうるが(佐藤千恵「判批」中京学院大学経営学部研究紀要24巻(2017)43頁)、他方で、請求異議の訴えが子の福祉を判断する手続としてはふさわしくないという理由から、積極的に推奨しなかったとの指摘もある(山木戸勇一郎「判批」法学研究87巻4号(2014)59頁)。」との指摘もあるところです(『家事法の理論・実務・判例4』勁草書房130頁)。
裁判例に目を向けると、「債務者は,未成年者が債権者に対する強い拒否的感情を示すとともに断固として応じない態度に終始していて,現時点において面会交流を強制することは,未成年者に情緒的混乱を生じさせ,その生活に悪影響を及ぼすと主張して,債権者と未成年者の面会交流は許さなければならないものではないとする。しかしながら,債務者が主張する事由は,請求異議の事由として主張しうるにとどまるものであり,また,本件審判後に生じたものであるならば,審判後に生じた新たな事情によって面会交流を行うことが子の福祉を害するものとして,事情変更による面会交流禁止を求める調停・審判の中で具体的に主張すべきものである。」とするものや(札幌家決平成24年9月12日)、「抗告人は、上記義務を履行しないことにつき正当な理由がある旨主張するが、同主張は請求異議の事由として主張し得るにとどまると解される。また、上記調停成立後の事情の変更により、相手方と未成年者の面接交渉が未成年者の福祉に反するに至ったと主張するならば、本件条項の取消しを求めるべき(調停ないし審判の申立て)である。」とするもの(大阪高決平成15年3月25日)などがあり、これらは債務者(同居親)による請求異議訴訟が可能であることを前提としていると見ることができそうです。
では、債務者(同居親)が請求異議訴訟を提起するとして、管轄裁判所はどこなのでしょうか。
この点については、債務名義ごとに管轄裁判所が決められており、確定判決・審判その他の裁判が債務名義の場合は第一審裁判所(民事執行法35条1項、33条2項1号)、和解調書・調停調書が債務名義の場合は成立した地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所が(同35条1項、33条2項6号)、請求異議訴訟の管轄裁判所となります。
とすれば、面会交流の間接強制に基づく強制金取り立てに対する請求異議訴訟の債務名義が何なのかが問題となりますが、前掲調査官解説に「どの債務名義に対する請求異議事由となるかについては更なる議論の深まりが期待される」とあるように、判然としないところがあります。
債務名義の候補としては、①間接強制決定、あるいは②間接強制申立ての前提となった面会交流の取り決め(調停調書、審判書、決定書、和解調書等)のいずれかが考えられそうです。
仮に①と考えた場合、請求異議訴訟の管轄裁判所は、間接強制申立てがなされた1審裁判所ということになるところ、間接強制の申立ては、調停又は審判等により面会交流を認めた家庭裁判所にされることになっています。
つまり、例えば、大阪家裁で成立した面会交流の調停調書に基づいて間接強制の申立てをするのであれば、大阪家裁が間接強制申立ての管轄裁判所となり、ひいては請求異議訴訟の管轄裁判所にもなるということです。
これが大阪高裁による決定に基づいて間接強制の申立てをするとしても、やはり間接強制申立ての管轄裁判所は大阪家裁となるので、請求異議訴訟の管轄裁判所も大阪家裁となります。
一方で、②と考えた場合はというと、上記の例でいうと、やはり大阪家裁が管轄裁判所になることが分かります。
ということで、債務名義を上記の①②のいずれと考えたとしても、請求異議訴訟の管轄裁判所は同じになると思われます。
請求異議訴訟を提起するタイミングについては、「請求異議訴訟は、債務名義が存在している限り、強制執行が開始される前から強制執行が完了するまで、いつでも提起することができる」とされています(『実践 民事執行法 民事保全法[第3版補訂版]』日本評論社67頁)。
9.執行停止決定の申立て
請求異議訴訟の提起と、強制執行の手続の関係については、次のように説明されています。
すなわち「請求異議訴訟を提起しても、執行手続は当然には停止しない。しかし、請求異議訴訟をしている間に執行手続が完了してしまっては訴訟の目的を達成できないし、執行手続が完了してしまっては訴訟の目的を達成できないし、執行手続が完了してしまえば請求異議訴訟は訴えの利益がなくなり却下されてしまう。そこで、債務者は請求異議訴訟を提起するとともに強制執行を停止する必要がある。そこで、裁判所は、異議の主張が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があったときは、終局判決をするまでの間、債務者の申立てにより強制執行の停止などを命ずる処分をすることができる(民執36条1項)。この仮の処分の申立てでは、債務者は請求原因だけではなく、予想される抗弁への反論や再抗弁も述べる必要がある。」との説明がなされています(『実践 民事執行法 民事保全法[第3版補訂版]』日本評論社68頁)。
強制執行停止決定の申立ては、請求異議訴訟の受訴裁判所(上記例でいうと、大阪家裁)に行います(民事執行法36条1項)。
また、急迫の事情があるときは、執行裁判所に対して申し立てることができるとされています(同36条3項)。
10.再度の面会交流調停・審判
子の福祉が問題となる事例においては、弁論主義の妥当する訴訟手続(請求異議訴訟)はなじまず、再度の面会交流調停・審判において丁寧に子の福祉を検討することが適切であるとの意見もあります(『家事事件における保全・執行・履行確保の実務』日本加除出版285頁)。
したがって、子どもが面会交流を拒否しているなどの事情があって、面会交流が実施できていない事例においては、同居親側としては、再度の面会交流調停・審判の申立てをすることも検討の余地があるといえます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。