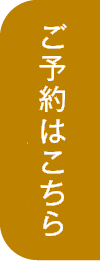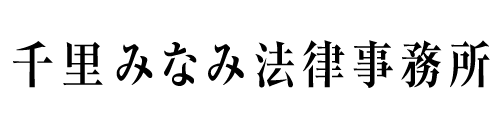【大阪の離婚弁護士が教える】子が奨学金を得ている場合の婚姻費用
子供が奨学金を得ている場合、その分、学費の負担が小さくなるように思えます。
そのため、婚姻費用の義務者側からすれば、奨学金を考慮して婚姻費用の額を決めてほしいと思うかもしれません。
では、実際はどうなのでしょうか。
今回は、貸与型の奨学金が問題となった裁判例を一つ紹介します。
【東京家裁平成27年8月13日審判】
長男及び長女の教育にかかる学費等を算定表の幅を超えて考慮するかどうか検討するに,相手方は,長男が私立の大学に通うこと及び長女が専門学校に通うことについて承諾していたものの,これらの承諾は長男及び長女が奨学金の貸与を受けることを前提としたものであったことは,上記第1の7で認定したとおりであるところ,上記第1の5ないし7で認定した事実によれば,長男及び長女は毎月12万円の奨学金の貸与をそれぞれ受けており,長男及び長女の教育費にかかる学費等のうち,長男の通う大学への学校納付金については全て,また,長女の通う専門学校への学校納付金についても9割以上,各自の受け取る奨学金で賄うことができる。これに,算定表で既に長男及び長女の学校教育費としてそれぞれ33万3844円が考慮されていること,相手方が,現在居住している住居の家賃の支払だけでなく,本件ローンの債務も負担していること,長男及び長女がアルバイトをすることができない状況にあると認めるに足りる的確な資料がないこと,当事者双方の収入や扶養すべき未成熟子の人数その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると,長男及び長女の教育にかかる学費等を算定表の幅を超えて考慮するのが相当とまではいうことはできない。
申立人は,長男及び長女が奨学金の貸与を受けていることは,相手方の婚姻費用の分担義務を軽減させるべき事情とはならないと主張する。
しかしながら,貸与とはいえ,これらの奨学金により長男及び長女の教育にかかる学費等が賄われていることは事実であり,しかも,これらの奨学金で賄われる部分については,基本的には,長男及び長女が,将来,奨学金の返済という形で負担するものであって,当事者双方が婚姻費用として分担するものではない(このことは,長男が相手方の別居を理由に奨学金の額を増額していたとしても,異なるものではない。)のであるから,奨学金の貸与の事実が,相手方の婚姻費用の分担義務を軽減させるべき事情にならないということはできない。
この裁判例では、婚姻費用の額を決定する(子の学費を考慮するか否か)に当たり、子どもが貸与型の奨学金を得ていることを考慮して、婚姻費用の額を決めていることが分かります。
結果的には、義務者にとって有利な形の認定となっているといえます。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。