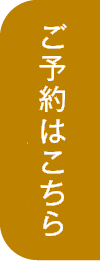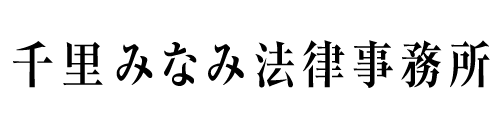【大阪の離婚弁護士が教える】婚費・養育費の算定において、義務者の収入を推計する場合
前回の記事では、権利者に潜在的稼働能力を認めて収入を擬制する場合について解説しました。
今回は、義務者側の収入を擬制する場合を取り上げてみたいと思います。
裁判例を一つ紹介します。
【大阪高決平成22年3月3日家月62巻11号96頁】
相手方は,歯科医であり,平成20年×月×日から平成21年×月×日までa病院に勤務し,給与及び賞与として,平成20年中は558万4439円を,平成21年中は191万0090円を支給された。相手方は,平成21年×月×日付けで上記病院を退職し,同年×月×日から大学の研究生として勤務しながら,病院でもアルバイトをしている。相手方は,同年中に大学から給料等として91万6600円を,アルバイト先の病院から給料及び賞与として117万1200円の支払を受けた。
(中略)
相手方は前件調停が成立してから×か月後に就職先を退職し,大学の研究生として勤務して収入を得る状況となっており,平成21年の収入は合計399万7890円となり,前件調停成立時に比して約3割減少していることを認めることができる。相手方は,退職の理由について,人事の都合でやむを得なかった旨主張するが,実際にやむを得なかったか否かはこれを明らかにする証拠がない上,仮に退職がやむを得なかったとしても,その年齢,資格,経験等からみて,同程度の収入を得る稼働能力はあるものと認めることができる。そうすると,相手方が大学の研究生として勤務しているのは,自らの意思で低い収入に甘んじていることとなり,その収入を生活保持義務である婚姻費用分担額算定のための収入とすることはできない。
上記裁判例を見ていただくと、義務者についても、働くことが可能であるのに働いていない場合、あえて低い収入に甘んじている場合などには、収入を擬制して婚姻費用や養育費を算出することがあるということがお分かりいただけると思います。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。