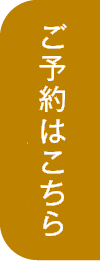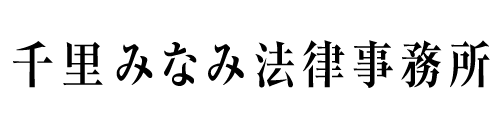【大阪の離婚弁護士が教える】不倫の証拠としてLINEを見ることは違法か?
不倫の証拠としてLINEのやり取りが提出されることが少なからずあります。
では、配偶者のLINEを見ることは違法とはならないのでしょうか。
今回はこの点が問題となった裁判例を紹介したいと思います。
【東京地裁平成30年3月27日判決】
この事件では、被告(不貞相手)は次のように主張しました。
(2) 原告は,被告とAとの不貞関係を裏付ける証拠として本件LINEデータ(甲2の1~3)を提出するが,その証拠収集方法が違法であり,証拠能力が否定されるべきである。
すなわち,原告は,平成26年6月2日頃,Fが所有する鴨川の別荘に不法に侵入し,インターネットに接続されていたA所有のパソコンを使用して,Aを利用権者として付されたGoogleアカウント(以下「本件アカウント」という。)のID及びパスワードをそれぞれ入力して本件アカウントにログインし(本件アカウントは,その都度ID及びパスワードを入力する設定となっていた。),本件アカウントの「Gmail」内のメールに添付されていた本件LINEデータを不正に取得したものであって,原告の上記行為は,建造物侵入罪(刑法130条)及び不正アクセス禁止法2条4項1号違反(不正ログイン)に該当し得る。
仮に,本件LINEデータの証拠能力が肯定されたとしても,本件LINEデータは単なるテキストデータであり,原告に都合が良いようにねつ造ないし改ざんが可能であるから,その信用性は極めて低い。上記(1)のとおり,被告がAと肉体関係を持つようになったのは平成26年5月以降であるところ,被告は,それ以前の段階で肉体関係にあることをうかがわせるようなやり取りをAとした記憶はない。そもそも,本件LINEデータの一部については,やり取りの相手方が「Unknown」と表示されており,被告とのやり取りかも疑わしい。
これに対して、原告は次のように反論しました。
(2) 被告は,原告の提出した被告とAとのやり取りに係るLINEのデータ(甲2の1~3,以下「本件LINEデータ」と総称する。)の証拠能力を問題とするが,原告の証拠収集方法に法令違背はない。
まず,建造物侵入罪(刑法130条)についてであるが,原告が入った建物は,原告及びAの家族のための鴨川の別荘であり,原告はその鍵を保有して,自由に出入りしてきたものであって,同罪に問われる余地はない(原告とAとが別居した後に,鴨川の別荘の所有名義がAの母であるFに変更されたにすぎない。)。また,原告が証拠収集に使用したパソコンについて,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「不正アクセス禁止法」という。)2条4項1号違反があったというが,原告において,パソコンにAのアカウントIDやパスワードを入力した事実はない。原告が使用したパソコンは,鴨川の別荘に置いてあり,家族が使用していたものであって,原告は,電源がついたままのパソコンを触ったところ,たまたまそこに保存されていた本件LINEデータを発見したにすぎない。
さらに,被告は,本件LINEデータの信用性についても問題とするところ,確かに,やり取りをしている相手が「Unknown」と表示されているものもあるが,その内容をみれば,お互いを名前で呼び合うなど,明らかにAと被告とのやり取りであるし,本件LINEデータが大量なものであることからすれば,これらをねつ造,改ざんすることは不可能であって,被告において,ねつ造等の箇所の指摘を一切できないことが,本件LINEデータが当時のやり取りそのままであることを示しているというべきである。
では、裁判所はどのように判断したのでしょうか。
裁判所の判断を見てみましょう。
1 まず,本件LINEデータの証拠能力について検討すると,民事訴訟に関しては,証拠能力の制限に関する一般的な規定は存在しない。この点,訴訟手続を通じた実体的真実の発見及びそれに基づく私権の実現が民事訴訟の重要な目的の一つであるとしても,同時に,民事訴訟の場面においても信義則が適用されることからすれば(民事訴訟法2条),訴訟手続において用いようとする証拠が,著しく反社会的な手段によって収集されたものであるなど,それを証拠として用いることが訴訟上の信義則に照らしておよそ許容できないような事情がある場合には,当該証拠の証拠能力が否定されると解すべきである。
そこで,本件LINEデータの収集方法について検討すると,被告は,原告が,①F所有の鴨川の別荘に侵入した上(建造物侵入罪に該当),②インターネットに接続されたA所有のパソコンを使用して,本件アカウントのID及びパスワードを入力して,本件アカウントにログインし,本件アカウント内に存在する本件LINEデータを取得した(不正アクセス禁止法違反[不正ログイン]に該当)旨主張する。
まず,上記①(建造物侵入)に関してみると,原告の原告代理人に対するメール(乙1)によれば,原告が鴨川の別荘において本件LINEデータを入手したのは平成26年6月2日であると認められるところ,〈a〉同時期は,原告とAとが別居を開始した約2か月後であるものの(前記基本的事実),原告はまだ鴨川の別荘の鍵を所持しており,それを使用して鴨川の別荘に入ったこと(弁論の全趣旨),〈b〉鴨川の別荘は,原告との婚姻後である平成23年3月にAが購入し,以後,A及びその家族の別荘として使用されてきたものであること(前記基本的事実),〈c〉鴨川の別荘のAからFに対する所有権移転登記は,平成26年6月27日(原告による本件LINEデータ入手後)に,平成25年6月26日贈与を原因として行われたものであるが,鴨川の別荘は,同日以降もA及びその家族の別荘として使用され続けたこと(甲8,9)からすれば,原告に建造物侵入の故意があったかどうかも定かではなく,また,鴨川の別荘への立入方法が著しく反社会的であると評価できるものでもない。
次に,上記②(不正ログイン)に関してみると,この点について,Aは,〈a〉鴨川の別荘に置いてあるパソコンは,自分専用のものであり,パソコンにログインするためにはパスワードが必要であるが,それは誰にも教えていない,〈b〉本件LINEデータは本件アカウント内にのみ保存しており(パソコンのハードディスクには保存していない。),それにアクセスするためには,本件アカウントのIDとパスワードを入力(ログイン)する必要がある,〈c〉本件アカウントのIDはAのGmailアドレスと同一であるので,同アドレスを知っている者であればIDを知り得るが,本件アカウントのパスワードは誰にも教えておらず,このパスワードはパソコンにログインするためのパスワードとは異なるものである(もっとも,いずれも,家族で共用している他のパスワードから類推することは可能なものであった。),〈d〉平成26年6月2日,鴨川の別荘内にあるパソコン及び本件アカウントがいずれもログイン状態にあったということはない旨供述する。しかしながら,仮に,上記のとおりであったとすれば,原告は,二重に存在するパスワードをいずれも探し当てて,本件アカウントにログインしたことになるが,いくら他で類似するパスワードを使っており,それを原告が了知していたとしても,上記行為を成し遂げる可能性は相当に低いといわざるを得ない。そもそも,原告が本件アカウントに係るパスワードを探知できるのであれば,原告は自分のパソコンを使用するなどして,本件アカウントにログインできるのであって,これを鴨川の別荘で行う必要性は皆無である。このことに,原告が,平成26年6月3日(本件LINEデータの入手の翌日),原告代理人に対し,「昨夜鴨川の別荘に行ったところ,運良く夫がログインしたままのPCがあったので,中を見てみました。旅行中に証拠隠滅されたLINEのやり取りが文字でご丁寧にフォルダーに分けられ保存されていました。そのデータと先週末,女性と別荘で過ごした?かも知れない写真もありましたので,一緒に送らさせていただきます。」というメールを送信していること(乙1)からすれば,原告が,自ら本件アカウントにログインして本件LINEデータを入手したとは認められない(原告が鴨川の別荘に立ち入ったときに,本件アカウントにログインしたままの状態のパソコンがあったか[乙1,32の1・2によれば,その約1週間前である同年5月25日にAと被告が鴨川の別荘を訪れていることがうかがわれ,失念等の原因から,本件アカウントにログインしたままの状態であった可能性は否定できない。],あるいは,パソコンのハードディスク内に本件LINEデータが保存されていたかであった可能性が高い。)。以上からすれば,原告が不正ログインによって本件LINEデータを入手したとは認められず,その入手方法が著しく反社会的であると認めるに足りる事情もない。
したがって,本件LINEデータの証拠能力は否定されないというべきである。
このようにして、配偶者のLINEを見た行為を違法収集証拠とはせずに、証拠能力を肯定しました。
そして、結果として、被告(不貞相手)に対して165万円の支払いを命じました。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。