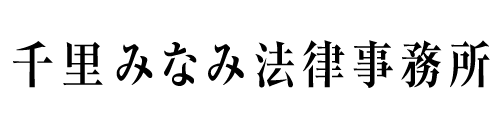【大阪の離婚弁護士が教える】悪意の遺棄に当たるのはどのような場合か?
民法が定める離婚理由の一つに「悪意の遺棄」というものがあります(民法770条1項2号)。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく民法752条の同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
しかし、これだけでは、どのような場面になればこれに当たるのかがなかなか分かりにくいかもしれません。
そこで、まずは悪意の遺棄が認められた裁判例を見てみたいと思います。
【浦和地判昭和60年11月29日判タ596号70頁】
1 被告は、昭和三二年ころ、鴻巣市内の○○新聞専売所で働くようになつたころから、些細なことで度々原告と口論し、原告に暴力を振うようになつた。このころ、原告は肺浸潤と診断され、三か月程実家に帰つて静養したが、被告の暴力行為はその後も止まず、昭和三三年ころには、原告を殴つてその手首の骨を折り、翌昭和三四年ころには、原告に時計を力一杯投げつけて額に五針も縫うような大怪我をさせ、更に、重い新聞の包みを原告の腹に投げつけたり、足で蹴つたりした。
2 原告は、昭和四六年ころ、体に変調を生じ、血液のバランスが悪いと診断されて約一か月間入院し、その後昭和五一年六月ころ、子宮癌に罹患していることが判明し、子宮体腫瘍と診断され、同月三〇日、埼玉県北足立郡伊奈町所在の埼玉県立がんセンターにおいて子宮全摘出手術を受け、その治療のため昭和五三年三月まで通院し、その間の昭和五二年八月一二日、原告は、それまでの過労や心労が重なつたためか、脳血栓と診断され、同日から同年九月一七日まで、上尾市仲町○丁目○番○○号医療法人○○病院に入院したが、結局、右半身不随になり、昭和五五年八月五日、埼玉県から脳血栓による右半身機能不全を理由に身体障害者第四級と認定された。現在、原告は右手が使えず、右足も利かないため歩行困難で、歩行するには杖が必要な状態である。
3 このような身体障害者である原告に対し、被告は十分な看護をせず、女性問題で原告を悩ませ、原、被告間に口論が絶えず、夫婦関係は次第に悪化して行つた。被告は原告に対し、「俺のものは全部やるから離婚しろ。」と怒鳴ることもあつた。その後の昭和五五年五月下旬ころ、被告は突然家を出、帰宅しなくなつた。その数日後、原告の兄や姉、被告の母親の説得で原告は一旦帰宅したが、一日で家を出、以来一度も帰宅せず、生活費の送金も一切していない。原告は、二世帯入居可能な本件建物(二)のアパートのうち一世帯分(他の一世帯分は日当りが悪く長期間空家のまま。)の家賃一か月金二万五〇〇〇円の収入と原告の親族からの借金で辛うじて生活し、日常の買物等は半身不随で不自由なため、右アパートの住人の好意に縋つてこれを頼んでいる。
以上の事実を認めることができ〈る。〉
右認定の事実によれば、被告は昭和五五年五月以来、半身不随の身体障害者で日常生活もままならない原告を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間原告に生活費を全く送金していないものであり、被告の前記行為は民法七七〇条一項二号の「配偶者を悪意で遺棄したとき。」に該当するものと言わざるを得ない。したがつて、原告が被告との離婚を求める本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がある。
【名古屋地判昭和49年10月1日判タ320号281頁】
1 〈証拠〉によると次の事実を認定することができる。
(一) 被告は、その先妻秋子(仮名)と昭和四四年九月二六日協議離婚したが、同女との間に長男一郎(仮名)(昭和三七年八月五日生、右協議離婚後のその親権者は被告)、二男二郎(仮名)(昭和三九年七月三〇日生、前同様その親権者は被告)があつたところ、自己が旅客誘致員として勤務する東急鯱バス株式会社でしり合つた原告(原告も当時同会社にバスガイドとして勤務しており、現在も勤務中)と昭和四四年九月二九日婚姻(の届出を)(原告は初婚)し、両名は被告の本籍地において被告の両親、被告の前記の先妻の子二人とともに結婚生活をつづけ、原被告間に長男三郎(昭和四四年七月四日生)をもうけていた。
(二) 被告は、昭和四五年二月頃から同年五月頃にかけて右会社の旅客誘致員として集金した金額二六三万二、九五〇円を、その頃同会社に入金せず自己の賭事等の遊興費として費消し、そのうち六六万六、〇七〇円を自己の親戚から借りて同会社に返済したが、右残金については返済の見込がたたず、止むなく、原告は被告と協力して両者の毎月の給料を合して、被告の給料分の殆んど全額を同会社への分割返済にあて、原告の給料分で親子三人の生活を支えることにし、同年九月頃から四八年六月頃にかけて右方法で分割返済をなし、原被告は右の残金とこれの遅延損害金合計二三〇万八、一九五円を完済した。
(三) ところが、被告は右の返済が漸く終ろうとする昭和四八年六月二四日頃原告に行先をつけずに突然家出して消息を絶ち、その後約一ケ月位たつてから一度家に寄りついたが、その際も原告に対し被告が何処で何をしていたかを全然知らさず、すぐさままた家を出てそのまま消息を絶つた。
(四) 被告の家出後、原告は被告の親との折合も悪くなり、被告が飲屋等他に借金を残したまま家出したためその取立などに責められたこともあつて被告の実家にいずらくなり、原告は同年七月末頃長男を連れて原告の肩書住所地の原告の実家に帰らざるをえなくなつたが、被告は現在にいたるまで原告に何らの音信もせず、その住所は不明で、もとより、原告の生活費等にあてるべき金員の送付等も全然しない。
原告としては、被告がどこかのスナックの女将と同棲しているらしいとか、時たま自己の実家にその様子をみるため立寄るらしいとかの噂を耳にするだけである。
(五) 被告は前記の不始末とは別に、昭和四四年六月二八日頃原告の父親からも仕事のためと称して九五万円を借りうけ、そのうち三三万円は返済したが残金の返済を今もつてなさないので、原告は自己の両親に対しても肩身のせまい思いをしている。
(六) 以上のような状態なので原告は被告との婚姻関係をつづけることを諦め、離婚を決意したが、原告は右のような被告の仕打により精神的打撃をうけ、また本件離婚につき幼い長男をかかえ、今後の身の処し方等についても非常な不安にかられ眠れぬ夜を送つている。
かように認めることができ、この認定に反する証拠はない。
2 以上の事実によると、被告は正当な理由なく原告との同居義務および協力扶助義務を尽さないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認めえないから、原告の本訴の離婚請求は被告の悪意の遺棄を原因とする点ですでに理由があり、また、右認定の事実関係の下においては、原告の申立のとおりの親権者指定をするのが相当である。
次に紹介する裁判例は悪意の遺棄を否定したものです。
【東京地判平成7年12月26日判タ922号276頁】
原告は、被告から悪意で遺棄されたことを第一次的離婚請求事由として主張しており、原告の慰謝料請求にも関連するので、1の点だけにとどまらず、離婚原因について判断する。
(一) 原被告の婚姻の問題点
前記二2のとおり、原告被告間の婚姻は昭和五八年三月に開始されたもの、同居期間は、昭和六〇年四月から同年七月までのわずか四か月間であった。生い立ちや考え方も必ずしも同一でない他人同士が一緒になるのであるから、同国人同士でも婚姻の開始に際しては、互いの理解に困難を来すこともあるのが婚姻一般に通例であると思われる。したがって、被告が日本語の読み書きができる等その日本語の理解力が相当程度であったと思われる点を考慮しても、原被告は、日本人とイタリア人という国籍を異にするのであるから、互いが互いを一二分に理解しようとする不断の努力と愛情の深さがなければ、婚姻関係を実りあるものに育てていくことに困難が伴うものといえるであろう。しかるところ、原告の医学生としての勉学の必要性から婚姻開始当初の二年間別居しなければならなかったのは、結果論であるが、大きな痛手であったといってよいであろう。そして、同居半年後に被告が出産予定となった時に、原告が医師国家試験に失敗してしまったことが見逃せない。ところが、このような困難に直面し、互いの結束を強くする必要のある最も重要な時期に、相互理解を深めた相互協力が十分にされなかったように思われる。被告は、経済面での不安や異国で妊娠出産に伴う諸問題を悩んだのであるが、原告に相談することが少なかったようであり、反対に原告は、被告の心情を思いやり、精神面での援助だけでも一二分にすることもなかったようである。
(二) 破綻状態の発生と原因
おそらくは、両者とも努力をしたと思われる。しかし、それは、互いの主観を基準にすれば十分といえる程のものであったかもしれないが、相手からみれば十分には感じられなかった程度のものであったのではないかと思われる。結果からみると、いずれが原因を作ったというより、国際結婚に伴う諸々の障碍とりわけ相互理解を深めることについて互いの性格及び能力がそもそも十分でなかったいう他ないのかもしれない。
この点に関し、原告は、昭和六〇年一〇月時点で未だ両者の関係が悪化していないし、また二3後段の書面は当時たまたまあったニュースをきっかけに被告から記載要請があっただけで、原告は本心でこれを記載したのではないと供述して、その後の被告の協力不足を指摘する。これに対し、被告は、この時点で既に両者の関係は相当に悪化していたと主張する。
被告が、出産を一か月後に控えた右の時点で、離婚を想定し、生まれてくる子の養育問題について、前記二3のとおりの書面に記載することを原告に求めたというのは、尋常のことではない。やはり、既にこの時点で両者の関係は深刻であったというべきである。
仮に両者の婚姻関係が良好なら被告がこのような不吉な内容の書面を記載して欲しいというはずがなく、被告の気持が深刻なものであったと考えるのが相当であろう。したがって、本心でなく記載したとの原告の右供述は採用することができない。仮に本心でないとの原告の右供述が真実なら、原告は、その時点での被告の深刻な気持を理解していなかったことになるが、そうなら、その点で、さらに被告の失望感を増幅させたかもしれない。
したがって、この時点で、原被告は、互いの関係の修復に最大限の努力をすべきであった。しかし、出産予定が近いせいもあり、また被告の両親が来日して被告の出産の応援にくるということもあり、原告が実家に移り、両者間の関係改善の努力はそれ以上されなかった。
子供が産まれた際は両名の関係改善のチャンスである。しかし、被告の両親が滞在していたためか、また医師国家試験が控えていたせいか、原告及び原告の両親は、被告及び被告の両親との率直な気持ちの交換の機会をあまり持たなかったようであり、原被告の関係改善は図られず、むしろ反対に互いを理解しないままに関係は悪化していったと思えるのである。
(三) 被告による本件子らのイタリア移住
子の出生後、被告は、母親と本件子らと共にイタリアに戻った。原告は、「被告が、その際、いかにも直ぐに戻るかのように騙してパスポートに子らの名前を併記することを原告に承諾させ、本件子らをイタリアに連れていき、原告から引き離した。」と供述する。〈原告本人調書一〇項〉
二4・5のとおり本件子らをイタリアに連れて帰り、被告だけは、一か月後に来日し、直ちに協議離婚を申し入れ、離婚調停を申し立てたことからすれば、被告は、日本を立つ前に離婚を決めていて子を先にイタリアに連れて帰るつもりで、原告の右指摘どおり、原告を騙してパスポートに本件子らの名前を記載させたかもしれない。このようなやり方は、原告からすると非常にアンフェアなものに感じられたであろう。
ただ、次のように考えることもでき、被告の右の態度は、原告が言う程に不当なこととはいえないとも思われる。すなわち、この当時被告だけが働いて収入があったのであるから、その被告が子の育児に専念するとなれば、仕事を断念しなければならず、収入源を断たれることになる。したがって、この問題をどうするかを早急に現実的具体的に解決しなければならなかったところ、原告がこの問題についての現実的でしっかりした解決案を呈示した形跡がうかがわれない。そこで、被告としては、ともかくも、子の養育を実家の母親に依頼することが先決問題であるとして、本件子を連れてイタリアに帰国するという選択しか取れなかったと考えた可能性が高く、その過程を原告にきちんと説明して了解を得なかったとしても、他に方法がなくこれを実行するしかないと考えていたとすれば、非難ばかりもできないことになる。事態を深刻に捉えていた被告とそれほどの事態とは考えていなかった原告との感性の違いかもしれない。
なお、イタリアに向けての帰国の少し前の昭和六一年一月に被告が原告に日本の保育園に入れるための手続を頼んでいること〈甲五・六〉からすると、その時点では、被告は、日本に残って原告と本件子らとの家族生活をするつもりでいたところ、結局その後に考えを変更して子を連れて帰ることにしたのかもしれない。仮にそうであるとした場合には、先の場合と同様かそれ以上の被告の苦しい心情がうかがわれるのであり、それを考慮すると、被告の態度だけを非難するわけにもいかない。
(四) 被告による悪意の遺棄の有無
いずれにしろ、被告にとっては、経済的及び精神的に原告から支援が得られるか不明であり、何よりも異国で家庭生活を営むことに伴う困難を互いの協力で乗り越えて行くだけの信頼感あるいは愛情の深さを原告に対して実感できなかったことになる。そして、その原因は互いの協力のレベルが深く強くなかったということになろうが、その責任を少なくとも被告だけに帰せしめ、あるいは被告の身勝手ということは酷であろう。原告にもなお至らない点もあったということができよう。
したがって、被告に悪意の遺棄があったというわけにはいかない。
以上見てきた裁判例からは、単に配偶者を残して家を出たというだけで「悪意の遺棄」に当たるのではなく、その前後の経緯も踏まえて判断されることが分かります。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。