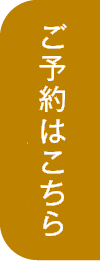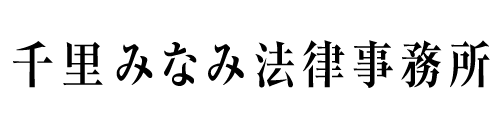【大阪の離婚弁護士が教える】家裁調査官の役割とは?
離婚事件や面会交流事件などの家事事件では、家庭裁判所調査官(家裁調査官)が関与することがあります。
この家裁調査官については、法律では次のように規定されています。
【裁判所法61条の2】
1.各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
2.家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
3.最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
4.家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
【家事事件手続法58条】
1.家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2.急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3.家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4.家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
【家事事件手続法59条】
1.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
2.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
3.家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
4.急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。
家事事件というのは、人間関係の対立から生じる紛争が多いため、法的な判断だけでは解決が難しいこともあり、心理学、社会学、教育学、社会福祉学等の専門知識を有する家裁調査官が事件に関与して解決に向けた支援をしていくという役割を果たしています。
調停室に入ったところ、調停委員とは別の人がいて、「この人は一体誰?」と思われることもあるかもしれませんが、それは当該事件を担当してくれる家裁調査官かもしれません(通常は冒頭で「家裁調査官の○○です」などと伝えてくれますが)。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。